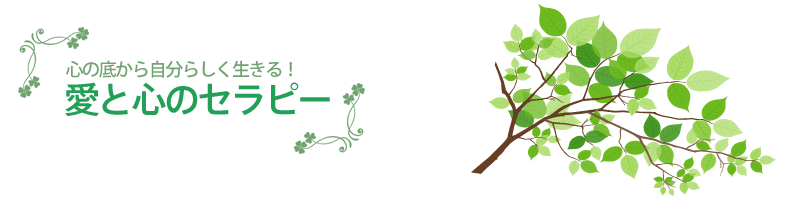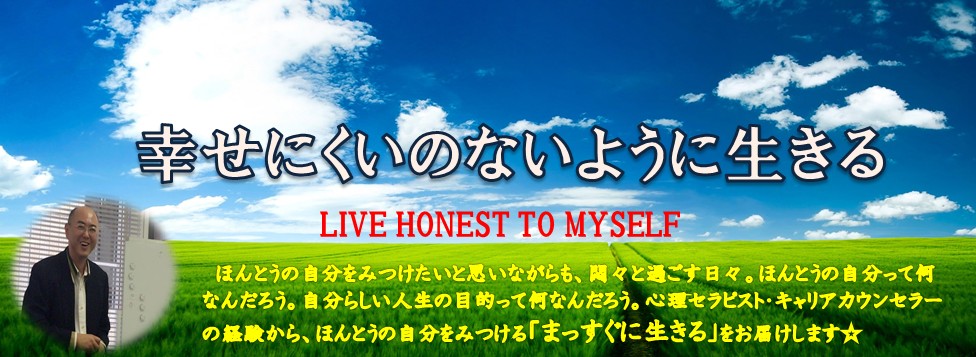「日本は便利になり若者がダメになる?」
『§幸せにくいのないように生きる』
「日本は便利になり若者がダメになる?」
先日床屋に行ったときの話である。
この床屋は三代続いている。
三代目の20代後半の孫が理容学校を卒業し、修行を終えてこの店に来てから、私の担当としてついてくれている。
もう今年もあっという間という会話から、流れでおせち料理の話になったのである。
「おせちって高いですよね。僕はおせち買うくらいなら好きな物を食べる派ですね」
彼はすでに結婚して子供も一人いる。
正月の元旦は、実家である父の家とお嫁さんの実家に行き、次の日からはちょっと贅沢な肉を頬張るとか。
両方の実家も、祖父がいるときは祖母と母が作っていたそうであるが、祖父母がなくなってからは、おせち料理を作る手間を考えると買った方がいいと、おせち料理は毎年買っているようである。
彼に私の家の話を少しした。
私の家では伝統を引き継ぎ、そう言うものだと思い込んで?はじめに食べる三品がきまっている。
“数の子と田作り(ごまめ)、たたきごぼう”である。
子孫繁栄の数の子。
片口イワシの稚魚を干して、飴炊きにした田作り。
片口イワシを農作物の肥料として使った田畑が豊作になったことにちなみ、五穀豊穣を願っているとか。
私が住む関西では“ごまめ”と呼び、「五万米」の字を当て呼ばれる。
そして、たたきごぼう。
地中深くに根が入っていくごぼうを食べて、家の基礎が堅牢であることを願うとか。
どれもこれもおせち料理には意味がある。
そんな話を彼にすると、会話が途切れた。
そして彼は言う。
自分がもの心ついたとこきには、スーパーが正月2日から開いていて、初詣には行くものの父が言うところの正月気分はすでになくなっていた気がすると。
それでも彼は、生まれ育った地元の床屋で働いているせいか、子供の頃からよく知ってる年配の方とも接しているせいか、けっこう昔の話にもついてこれて、なかなか話が面白いのである。
まあ、聞くところによると、おせち料理が今のように定着したのも江戸時代と聞くと、時代に流れの中で、風習も変わってくるにもいたし方がない気もする。
ただ、“感謝”に対する大切なこだわりのある私にとって、数の子、田作り(ごまめ)、たたきごぼうといったおせち料理には意味がある。
そこには”感謝の念“が込められていることが、忘れ去られて行くことには、寂しさ以上に危惧を覚える。
理容師の彼が、来年か再来年あたりからスーパーが3日から開くと言った時、「コンビニがあるから別に不便ではないですけどね」と言った言葉に、今の若者の世代を感じる。
日系ブラジル人二世で、ブラジル・サンパウロ出身の元プロサッカー選手で、現在テレビ東京(テレビ大阪)系列のスポーツ番組のサッカー解説もしている、セルジオ越後氏が私の知る大先輩に語ったこんな言葉を聞いた。
「日本は便利になって若者はダメになる。24時間開いてるコンビニも、あれは若者をダメにする。好きな物だけをいつでも好きな時間に買えたら、人間の心が育たたなくなる」と。
もう今の時代、若者に限った話ではないかもしれないが、学生と約20年関わって来てそれを痛感している今、彼らが担っていくこれからの時代。
『幸せにくいのないように生きる』ために、様々なことが便利に容易に手に入る時代に、感謝という“有り難み”を知る機会が、必要不可欠のように日々接していて思うのである。
最後に、最近“ありがとう”の反対は、“当たり前”と言う言葉をよく耳にする。その言葉だけが、拡散していく。
ただ“ありがとう”の心は、いつも当たり前に持っているべきものである、
と思うのだが。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,950 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,108 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,033 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,690 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,668 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,322 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,828 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31