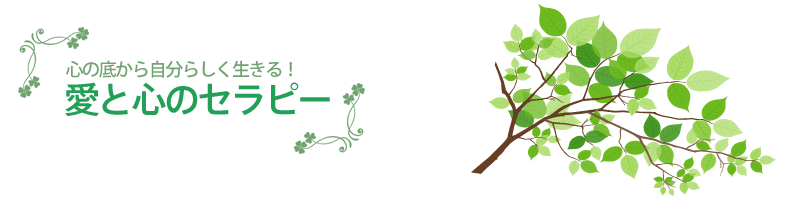「男性不信を乗り越えて」-プロローグー
☆この物語は、男性のことが信じられなくなった一人の女性が、和尚との対話で自分を取り戻すお話です。
※この物語は経験をもとにしたフィクションです。登場する人物、団体等は実在するものとは関係ありません。
‐プロローグ‐
薄っすらと屋根に雪化粧。寒々とした黒っぽい瓦に、白い雪が冬の風情を醸し出している。
何百年続くお寺の本堂の瓦は、そんな白い雪で覆われていた。
「今年何度目の雪景色だろう。」と、住職の光曉(こうぎょう)和尚は呟き、「あの子は今頃どうしておるのか。あの子がここへ来た日もこんな雪の日だったな。」と、粉雪が舞う庭を眺めながら当時のことを思い出していた。
女の子が初めてここへ来た時、彼女は高校3年生だった。大人っぽくてかわいらしい女性だった。しかし、彼女は冴えない悲しげな表情をしていた。
お参りに来たわけでもなさそうな雰囲気を察した光曉和尚は、「寒いのにようお参り。」と、女の子に声を掛けた。
女の子は和尚の顔を見てホッとしたのか、「生きているのが辛いです。」と言った。
ただ事ではないと思った和尚は、冷静な面持ちで、
「さあさあ、寒いからそっちの温かい部屋でお茶でもいかがかな。そうそう甘いものもあるから、私も今からお茶を頂こうかと思っていたんで、一緒にどうかな。」と、女の子に声を掛けて暖かい母屋へ来るように促したのだった。
女の子は落ち着きを取り戻したのか和尚に、「小さいころからびっこを引いていて、みんなからからかわれて、男の子からは気持ち悪がれて。」と、下を向きながら自分の心情を打ち明けたのだった。
光曉和尚はその時女の子の足が治るかもしれないと、知り合いの接骨院を紹介してあげて、桜の咲く季節には見事女の子の足は普通に歩けるようになったのだった。
和尚は彼女がその報告に来て、嬉しそうにこの境内で飛び跳ねて、喜びに満ちた顔をしていたのを思い出していた。
それから10年後のある日、再び彼女が光曉和尚に会いに来た。
彼女は見違えるほど綺麗な女性になっていた。和尚は名乗られるまでその女性があの時の女の子とは分からないほどであった。
そして閉口一番彼女は、光曉和尚に言った。
「私、男の人が信じられない。」と。
つづく
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,954 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,034 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,691 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,669 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,323 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31