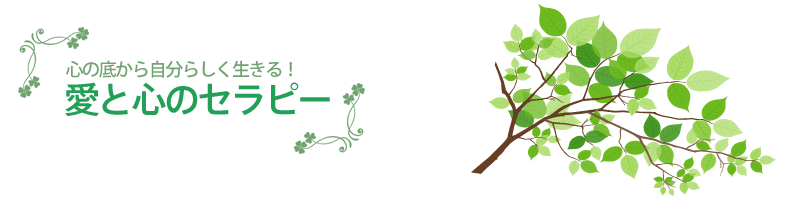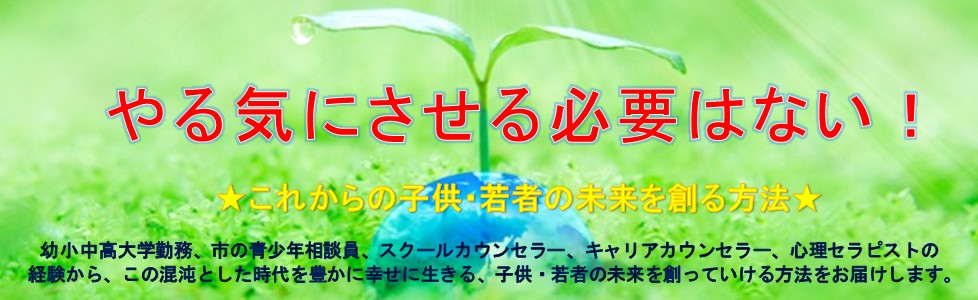子供の自ら学び、自ら考える力
子供の自ら学び、自ら考える力
今回は、子育てに話を戻して、自己肯定感と「勉強と遊ぶ」についてと
お話していましたが、その前に、この「自ら学び、自ら考える」ことに
ついて触れておきたいと思います。
この10年、若者に対して社会人基礎力として、社会の変化に主体的に
対応できる力として、「自ら学ぶや、自ら考える」の言葉をよく聞くよう
になりました。
もう少し具体的に言いますと、「
課題発見力」や「計画力」、「創造力」が当てはまります。
今の経済的にも物質的にも成熟した社会では、
もはや通説になっているようです。
この「自ら学ぶ、自ら考える」力は、いつ頃から公に言われるように
なったと思われるでしょうか。
実は、今から四半世紀(25年)前の1989年に、
文部省(現文部科学省)が学習指導要領の改訂の中で、
「新しい学力観」として提唱しました。
1989年とは、昭和64年であり平成元年の年です。
4月1日からははじめて消費税3%が導入された年です。
この年に文部省は、「社会の変化に主体的に対応できる」
子供を育てようという方針を打ち出したのです。
2002年に「ゆとり教育」がはじまったように思われがちですが、
実は1977年に戦後の「詰め込み教育」の反省に立ち、「ゆとり教育」
へと転換されました。
その後、1989年、1998年の改訂を経て、2002年からの
「ゆとり教育」は、本格的に知識を教え込む教育から、子供たちが自ら学び、
自ら考える力をつけようという理念にもとづいて実施されたのです。
そして現在、2008年の改訂で「脱ゆとり教育」となっています。
しかし、理念となる文部科学省が今も重点を置いているのは、
「習得した知識を活かして、自ら考え、課題発見をして解決したり、
実現したりする創造的な資質や能力」を重要なものとして考えています。
さて、今私は「自己肯定感を高め続ける」ことが大事だと、
『ありがとうの効果と秘訣』をとおしてお話していますが、
「学力=生きる力」は、本来密接な関係をなしてはいますが、
「学力≧生きる力」、もしくは「学力>生きる力」と、
歴史は繰り返されているように思うのは、私の思い過ごしでしょうか。
子育てという教育からみても、私たち一人ひとりが、
「これからどう生きるか」を問われているのかもしれませんね。
いつもお読みいただきありがとうございます。
次回は、もう少し子育てと自己肯定感について、
「勉強と遊ぶ」をお話したいと思います。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,954 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,034 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,691 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,669 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,323 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31