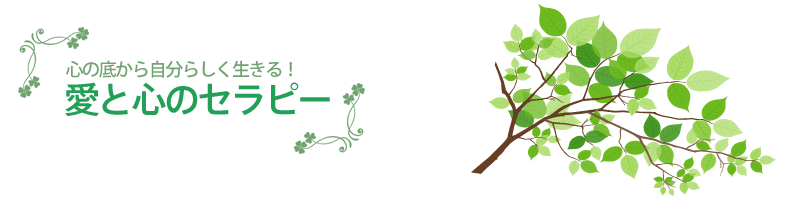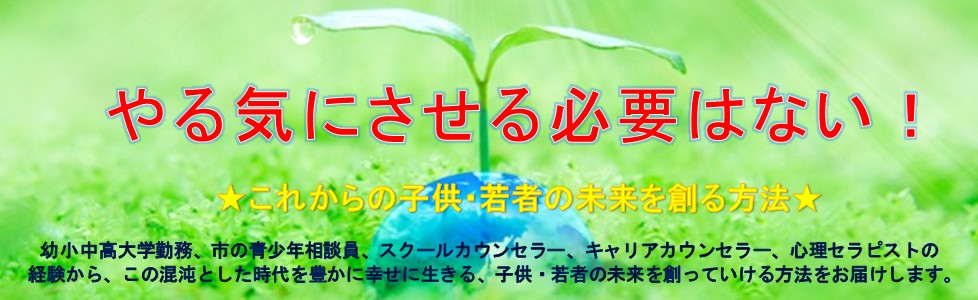「子供の未来(就職)を考える親のススメ」
就職しないできない若者の『未就職予備軍のレジリエンス(回復力)をどう引き出すか?』、キャリアカウンセラー・心理セラピストの観点から、子供や若者よりも、私たち大人に焦点を当てたお話です。
『Ⅸ.就職しないできない若者』
「第35話:子供の未来(就職)を考える親のススメ」
今の現実の日々、そしてこれからの時代を考えると、私たちや子供たちは、もっと便利でらくで簡単に、自我の都合のいい満足を満たす情報に溢れ選択肢が多い環境の中で、いかに取捨選択しながら最善のものごとを選択して生きていくかが大切になってきます。
それは裏を返すと、私たちや子供たちも、自らしっかりと考えなくても生きられる、周りに流されやすい社会ということです。
それだけに、今までのように外からの動機づけから心を豊かにするのもいいですが、そこに偏ると自らあまり考えることはせずに、社会に依存しきってしまいます。
そのためにも、これからは親や私たちが知らなかった、自分の内から創り出す心の習慣のすべを身に付けること。
心に余裕のある生き方をするために、自己肯定感を高めた状態を心のベースにすること。
親や私たち大人が理性(人としての道理)を持って主体的にものごとを決めることのできる、「自らの人生をどう生きるか」身を持って体験しながら子供たちに教え伝えていくこと。
それが子供の豊かな発想力や前向きにものごとを考え、主体性を育む最大の教育になっていき、子育ての早道になること。
そして、つまるところ『感謝を笑顔でできる心』なのです。
それらを踏まえて、子供の就職について考えてみたいと思います。
親が子供を育てる一つの大きな強い思いは、子供の社会的経済的な自立と、言ってもいいかもしれません。
そこにあるのは、子供が社会で『働くこと』であり、少しでもよりよい条件で働いてほしいと思って、子供に勉強してほしいと思っているのではないでしょうか。
私自身も少し前までは、「社会的経済的な自立」と思っていましたが、近年の若者の傾向を見ていると、そこの親や私たち大人の意識も変えていかないと、いけない時代になってきたように思います。
今、私は有名国立大学の大学院生から専門学校生まで幅広い層の学生と留学生のキャリアカウンセラーとして(心理セラピストの観点も踏まえて)、日々学生の就職支援をしています。
私が約15年前に学生と関わっているときと比べると、今の学生の傾向として卒業すれば『働くこと』は、もう言わずとも知れず当たり前の事実に思っているように感じます。
それよりも学生と接していて感じるのは、『自らの人生をどう生きるか』ということです。
意外に感じるかもしれませんが、言葉で(表面意識)で話す学生もいれば、自分の気持ち(潜在意識)を上手く言語化できないですが、言葉尻から伺い知ることがあります。
つまり、社会に出て働くのは、昔と違ってご飯を食べることが目的ではなく、それは当たり前の大前提にあって、『どう仕事にやりがいを持てるか、会社や社会に貢献・役立てられるか』という強い思いを感じます。
そう考えられる理由として、次のような「世代間ギャップ」が言われます。
「アナログ時代 → デジタル時代」
「欠落感から豊かを志向 → 生まれたときから豊か」
「努力すれば幸せになれる → 今を楽しむ安定志向」
「目標達成・手続き重視 → ノンプロセス」
「世間の評価が大事 → 自分らしさが大切」
「食べるための仕事 → ライフスタイルと仕事は一致」
これだけ見ても、親の世代と子供の世代の生きる価値観が、違っているのはわかるのではないでしょうか。
これらのことを理解して上で、これからの「子供の未来(就職)を考える」ことがポイントになってきそうです。
さらに公的機関が公表している分析データからも伺い知れるのですが、そのお話は次回にしたいと思います。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,954 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,033 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,690 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,668 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,322 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31