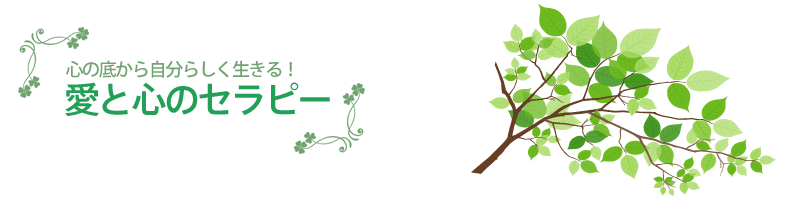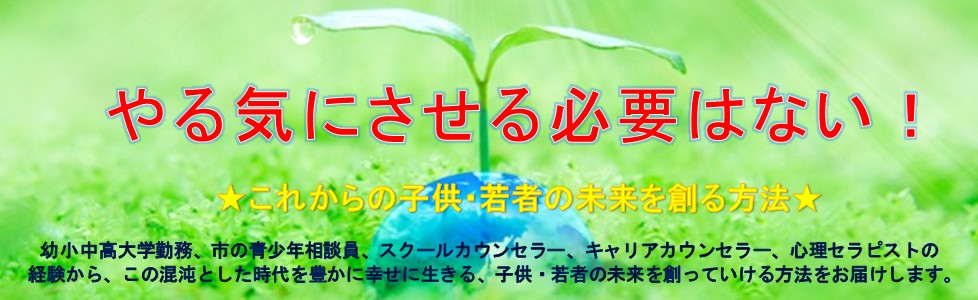「人生の目的を生きる基盤を創る①」
就職しないできない若者の『未就職予備軍のレジリエンス(回復力)をどう引き出すか?』、キャリアカウンセラー・心理セラピストの観点から、子供や若者よりも、私たち大人に焦点を当てたお話です。
『Ⅸ.就職しないできない若者』
「第45話:人生の目的を生きる基盤を創る①」
【親が自己肯定感を高めた心の習慣を創ること。
それが子供の豊かな発想力や前向きな考える力、
主体性を育む最大の教育になり、子育ての早道。
つまるところ、『感謝を笑顔でする心』である。】
前回、「人生の目的を生きるのが難しいわけ」の最大の理由は、不安からの『恐れ』というお話をしました。
また、ポジティブで自己肯定的になり、精神的にも心が安定していて、気持ちも高くなっていて、本来の軸がぶれない自分自身の状態をつくるために、自分の外に答えを求めようとし過ぎると、思考や習慣が受身的になってしまう。
この受身的な心の習慣は、他律的(自らではなく他によって律せられる)になり、自分軸を他人に預ける度合いだけ、心に不安という「恐れ」を生みやすくする。
そのためには、受身的な心の習慣から「主体的」になること。他律的ではなく「自律的」になること、というお話をしました。
そこで、この心の習慣を日々の生活の中で、自らがいつでもいい状態を創りだすことができれば、それ以上のことはないのではないでしょうか。
今回は、その解決する方法として、日常の中でも、ポジティブで自己肯定感が高く、精神的にも波動が高くなっていて、本来の軸がぶれない状態をつくればいいという、その具体的なお話をしたいと思います。
ことは簡単なのです。毎日朝起きてから、ポジティブに気分が穏やかになることをすればいいのです。
そんな言葉を唱えればいいのです。毎日歯を磨くように、言えばいいのです。
歯を磨かないと気持ちが悪いように、習慣化してしまえばいいのです。
私はあるとき思ったのです。
お坊さんを見ると、ほとんどの人が穏やかな雰囲気をしていると。
「なぜなんだろう」と思って考えていると、毎朝必ず朝のお勤めとして、お経を唱えていることに関係があるのではと思ったのです。
お経とは生きるための知恵が書かれていると、聞いたことがあります。
つまり、前向きな言葉が書かれているわけです。
そんなある日、両親の月命日にお坊さんがお経を唱えにやってきました。
バタバタとした日常の中で、しかも晩御飯前に来るとあって、せわしくしているときに用事を中断して仏壇の前に腰をおろします。
お経は時間にして約15分なのですが、そんなときの気持ちは、やたらと時計の針が気になったりして、なかなか落ち着かなかったりします。
そうこうしいるうちに、お経を聞いているのか、ただ時が過ぎるのを待っているのかわかりませんが、ふと内観(自分の心と向き合う)をしている自分がいるのです。
お経が響き渡る中で、どうやら内観することによって、心が穏やかになっているのです。
そして思ったのです。これが毎朝、しかも365日お経を唱えているとしたら、それも何年も続けているのであれば、日々の積み重ねの中で、心穏やかとい自己肯定感の高いポジティブな心の状態を、ぶれない軸をつくるのだと。
お経の例えを出しましたが、私たちは日々の生活の中で、どれぐらい意図して自己肯定感を高めるような時間を、持っているのでしょうか。
日々慌ただしく追われ、ストレスを感じやすい現代社会の中で、私たちはひょっとしたら、笑顔さえしていない日があるのかもしれません。
笑顔は、自己肯定感を高める三大方法の一つです。
一日を振り返り、微笑んだり笑顔になった数を数えられない度合だけ、私たちはネガティブな影響を受けやすい状態で生きているのかもしれません。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,948 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,108 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,032 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,689 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,667 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,321 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,263 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,129 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,864 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,827 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31