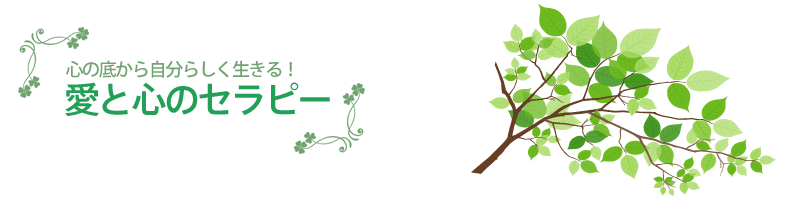自分の中にある可能性に気づこう~その3~
第一の法則『自分の中にある可能性にきづく方法』
「自分の中にある可能性に気づこう ~その3~ 」
私は、彼に違う見方でたこ焼きを焼いてることへのヒントになればと思い、話しました。
「あるお寿司屋さんで、 見習いの若い男の子が、アナゴの煮汁を作っていました。
完成したので、大将に味見をしてもらいました。
すると大将は『甘みがたらん、味が薄い』と、厳しい口調で言われました。
大将は彼に『味付けにマニュアルはない。 自分の舌や体で覚えんとあかん。
ある程度までの分量は計算できるが、 その先の微調整の味付けは、 自分の舌と体で覚えた経験がすべてや。
だから季節や天候、雨の日と晴れの日とでは 醤油と砂糖の分量は違う。
味見をする前に刺激物の多いものを食べたら 舌が麻痺して話にならない。
それと自分のその日の体調によって 味の濃さが微妙に変わってくるんだ』と」。
私は、彼にたこ焼を作っているときにも、 このような経験がなかったかと聞きました。
すると、彼はしばらく考えた後、 笑顔でたくさんのことを思い出して話してくれました。
「初めは、先輩の見様見まねで焼くことに必死でした。 慣れてきて自分が粉の調合からすべてを任されるようになったんです。 あるとき、たこ焼きを焼いていると、晴れの日と雨の日とでは、 水の配合が微妙に違うことに気がついたんです。
晴れて乾燥しているときと、 雨の日の湿度が高いときとでは、 鉄板の油ののりが焼いていて何か違うんです。 くしで回すときの感じが微妙に違うんです。
晴れて乾燥しているときと雨の日とでは、温度調節も微妙に違うんですよ。
晴れて乾燥していると微妙に焼きが早く焦げやすいし、 雨の日は温度を上げすぎると外だけ焦げて中は焼けていないので、 じっくりと焼かないといけないんです。
この温度調節が、 けっこう慣れるまで自分が思うようにできなかったんですけど。
あとそれにその日の気分によって、 溶いた粉を鉄板に流し込むときに微妙に手元が狂って、 粉の量が多すぎたり少なすぎたり、 自分のイメージ通りにいかないことがあるんですよ」と。
彼は、今まで当たり前のように無意識にたこ焼を焼いていましたが、 このことがきっかけで、仕事への取り組む姿勢が変わっていったそうです。
その後彼と何度か会いましたが、 会うたびに彼の表情はいい方向に変わっていき、 明るさと自信に満ちた男らしさを感じるようになっていきました。
その後の彼については、次回「自分の中にある可能性に気づこう ~その4~ 」へつづきます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,954 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,110 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,034 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,691 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,669 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,323 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,265 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,866 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31