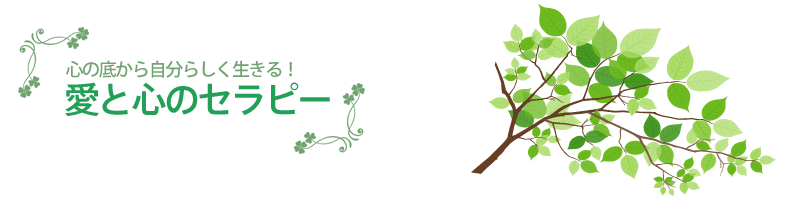物語メソッド実践編:「和尚との心の掛け違い」
◆心の底から自分らしく生きるメソッド(実践編)◆
「光曉和尚の愛と心のセラピー物語」
~私、自分らしく人生を生きます~
§ 和尚との心の掛け違い
前回、瑞枝は有里に抱き付かれるように号泣され、傍観的になっていた自分を有里の気持ちに寄り添うことで、瑞枝は何かを感じたのか目からは一筋の涙が流れ、それはいくつもの筋となって流れ落ちていったのだった。
和尚は瑞枝を見ながら、本人はなにが起こっているのか頭ではかわからないだろうと思った。それは、まるで今まで抑え込んでいた感情という風船が表に飛び出さないように、いくつものロープで固定されていたものが、知らぬ間に一本ずつ紐解かれていっているように思った。
瑞枝にとっては、意識して自分の抑えている感情を表に出すのはタブーだと思っていたので、自分の意識ではわからないところで起こっているこの状態を理解することができないのは当然のことだったが、和尚は瑞枝が有里の気持ちに触れることによって、ようやく本当の自分と向き合える心の準備ができてきたのかなと、思った。
有里は落ち着きを取り戻し、
「瑞枝ちゃん、ごめんね。自分でもよくわからなくて、気がついたら瑞枝ちゃんに抱き付いて泣いてた。いい年をして恥ずかしいね、本当にごめんね」
瑞枝は、首を小さく左右に振って有里を見ていた。
「ハアー、なんか脱力感。久しぶりにこんなに泣いたわ。昔ね、私10年ぐらい前までかな、ほんま泣き虫やったんよ。すぐ傷ついて泣いてた。今でこそこうなったけど」
和尚は、有里の本心からの言葉が、瑞枝の心にも響いているのかいないのか正直わからなかった。
瑞枝はというと、自分が苦しくて辛くて悲しい気持ちを思い出して、思わず涙がこぼれてしまった。同時に、自分が人前で泣いてしまって自己嫌悪になっていた。
「瑞枝ちゃん、ほんまにありがとう」
「いえ、私はなんにもしてないです」
「ううん、受け止めてくれるだけで嬉しかったんよ」
「私は感謝されるようなことは、なんにもしてないです」
和尚は、瑞枝が素直に有里の気持ちを受け取らないことに言った。
「瑞枝さん、人は自分の素直な気持ちを受け取ってもらえないとき、とても悲しくなるんですよ。瑞枝さんの口癖でもある“でも”という言葉は、“相手の気持ちを受入れません”と言っているのと同じなのですよ。
“でも”ということは悪いことではないけれども、まずは“Yes”と受け入れてあげてから、“でも”を言うと、それだけでコミュニケーションが全然違ってくるのですよ。
例えば瑞枝さんが私に、
『これとても便利ですから是非試してみたほうがいいですよ』と言ったときに、
『でも、私はいいです』と言われるのと、
『ありがとう、でも、私はいいです』とか、
『へーそうなんですか、でも、私はいいです』と言われるのと、 どちらが気分いいですか、ということなのです。
言葉は習慣の問題ですから、この“Yes, but”という法則を自分にとって役に立つと思ったら選択し直して、今日から使ってみるようにしはどうですか。気分がいいほうを選択するということは、また一つ自分に幸せになることが増えることですよ。
瑞枝は、和尚に“Yes, but”を使った方がいいと言われて、
『そんなこと言われなくても知ってるし、日頃はそういうふうにしてるし。そうじゃなくて、うーんうまく言えないけど、自分が人の役に立てるような、感謝されるに値しない人間ってわかってるから、私の本心とは裏腹に相手に合す自分が嫌だし、そんな自分の心が醜いし。
そんなことを思ってる私に“嬉しかった”とか“ありがとう”と言われても、“Yes”って相手の気持ちをまず受け入れるなんて、偽善ぽくってそういう気持ちになれるわけがない』と。というより、自己嫌悪になっているところに、そんなことを言われて余計にイラッとしたのだった。
和尚は、瑞枝がそんなことを考えていることなど知るはずもなく、瑞枝は有里の気持ちに触れることによって、自分の感情を少し解放できたのだと思っていた。そして、和尚は話を進めていった。
瑞枝さんはこんな話をすると、“ありがとう”を5つ言う(「それができたら悟ってるわ」参照)ところでも言っていましたが、『頭ではそういうふうにした方がいいと思っていても、気持ちがついてこない。
だからそう思っていてもできない』と思うかもしれません」と言って、和尚は新しい慣れないことに抵抗する心の話をし出した。
「面白いことに、瑞枝さんが『自分は人の役に立てれる、感謝されるに値する人間だ』と心で思えるようになったからといって、思考の言語システムは、習慣としてインプットされているので、心に反して慣れ親しんだ“でも”という表現をまた使ってしまうのです。
例えば、エスカレータで大阪と東京では、エスカレータの乗る立ち位置が左右違いますよね。瑞枝さんが東京へ行って、なにも考えずにエスカレータに乗れば、当然大阪の人は左側に立ちます。
そこで東京では右側に立つことを知って、東京に居る間は右側に立つように意識して習慣付けようとします。でも、またなにも考えずに乗ったときには、今までの大阪で慣れ親しんだ左側に立ってしまうということです。
つまり、思考を変えたからと言って気持ち(心)も変わるわけではなく、また気持ち(心)を変えたからと言っても思考は前のままになっている、というわけです。
この思考と心の不一致みたいなものが、“手間が掛る”感覚になるのかもしれませんね」と言って、和尚は一呼吸入れた。
瑞枝はイラッとした気持ちのまま、
『どうせ人の気持ちなんて所詮わかるわけなし。私はありがとうと言おうとしたら、感謝することが思い浮ばなくて、やっぱり心まで腐ってる最低な人間だから、なんでもいいって言われたけど、そんなことしか出てこない自分が情けないし、出てこないから適当なことを言っている自分が偽善ぽくって嫌になるし、ただ言われていたから言うようにしたけど、そんな気持ちでついてこないから毎日やるのが億劫』
と思っていたものの、そこは顔には出さずに和尚の話を聞いていた。
瑞枝は、どうせ心の内をわかってもらえないもどかしさに、『やっぱり私は・・・無理なんかも』と、落胆する思いだった。
つづく
次回明日10月9日(水)は、
物語メソッド実践編:「わかっているけどできない理由」をお話します。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。 心より感謝いたします☆
※この物語の後半は、実話にもとづいたフィクションであり、登場する人物など、実在のものとはいっさい関係がありません。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,954 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,110 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,034 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,691 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,669 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,323 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,265 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,866 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31