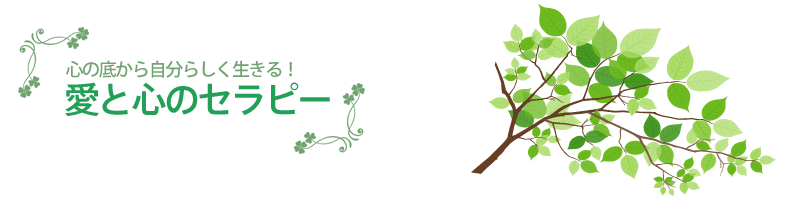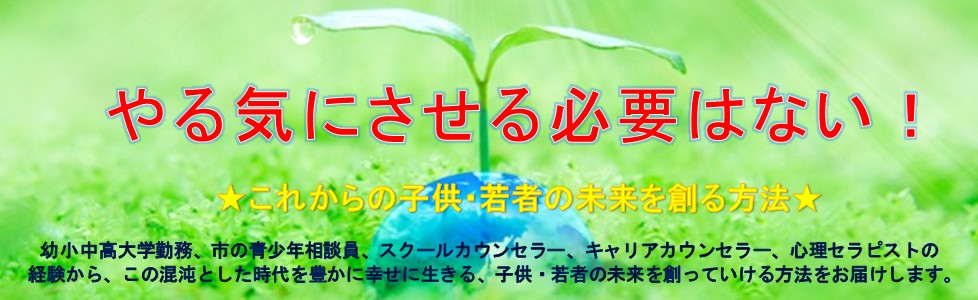「有り難味が希薄していく私たちの岐路③」
親が自己肯定感を高めた心の習慣を創ること。それが子供の豊かな発想力や前向きな考える力、主体性を育む最大の教育になり、子育ての早道。
つまるところ、『感謝を笑顔でする心』を親である私たち大人が育むことである。
『Ⅸ.就職しないできない若者』
「第75話:有り難味が希薄していく私たちの岐路③」
就職しないできない若者の『未就職予備軍のレジリエンス(回復力)をどう引き出すか?』、キャリアカウンセラー・心理セラピストの観点から、子供や若者よりも、私たち大人に焦点を当てたお話です。
前回、私たち大人が「なにを大切にして、どう生きるか」、その生き方が私たち自身のこの混沌した社会の「希望」になり、その生きる姿が子供や若者への生きる「希望」なる、というお話をしました。
今回は、さらに、この岐路の時代を生きるためには、どうすればいいのか、どうすればもっと生きやすくなるのかについて、お話したいと思います。
「有り難味が希薄していく私たちの岐路①②」のお話で過去の歴史を振り返り、私たちの時代は、物質的な豊かさを求めた物質的価値観の観念を基に生きて来ました。
物質的な豊かさに心が満たされて来ると、私たちの意識は外的な物質的なことからは満たされない限界を感じ出し、内的な精神的な心に意識が向き始めました。
それは、「自分らしさ」や「あるがまま」「やりがい」「生きがい」「人生の目的」といった形で現れてきました。
しかし、一方で物質的なものにあふれた社会でものが売れなくなると、さらに私たちが豊かな生活を送るために、サービスと利便性という形で、私たちの心に働きかけるように生活の一部となっていきました。
そのサービスや利便性の向上は、私たちの暮しにらくさと簡単さによるより快適な生活をもたらしくれる反面、ますます物質的価値観に依存していく危険性を持っているのです。
私たちの生きる時代は、冷静に客観的に見ると、今までの歴史上にない物資的な豊かさのいいところと、精神的な豊かさの大切さの両方に気づいてしまったのです。
私たちは、物質的な生き方に偏ると精神的な心がざわめき、精神的な生き方に偏ると現実的でもある物質的な生き方との乖離に、なにか違和感を覚えているのです。
これは、私たちの多くの人の潜在意識の中で起こっていることですが、一方ですでに表面意識(思考)で理解している人は、なにかしらの行動を起こし出しています。
ここに、これからを生きる岐路の意味が隠されているのです。
以前にも触れましたが、人はらくで便利で簡単なことの生活に慣れ親しんでしまうと、深く考えたり、想像したり、判断したり、主体的に行動することが低下していきます。
その低下は、自分にとって都合のいい悪いという“欲”でものごとを選ぶようになり、自分勝手な振る舞いや人を思いやることの欠如にもつながり、最後はどんどん社会と分離していってしまうのです。
今の世の中を見渡すと、すでに進んでいる傾向にあるのではないでしょうか。
子供や若者にその傾向が見受けられるように思いがちですが、実は私たち大人の方が物質的な豊かさの恩恵を経験し、その幸せに執着してきただけ、この低下の危険性をはらんでいるのです。
今の子供や若者は生まれた時から物質的な豊かさの中で生まれ、意外と物欲が少ない傾向にあると言われています。
それだけに心は柔軟であり、「自分らしさ」や「あるがまま」「やりがい」「生きがい」「人生の目的」といった内的な精神的な意識には、実は敏感なのです。
当たり前の生活の中で失われていく、根底にある価値観である「感謝」という有り難味の希薄化は、人口構成を見ても大人の方が圧倒的に多く、それだけに社会に与える影響も大きいことには、私たち大人は気づいていなのです。
そのような観点から見ても、
今の社会を創り出して来たのは、私たち大人なのです。
私たち大人が陥る罠は、いつの時代も自分が生きて来た経験でものごとを測る傾向にあります。その教訓が功を奏する場合も多くありますが、同時に客観的に木の上に立って見る、時代を見据えた上での的確な教育が子供たちには必要なのです。
だから、子供や若者を変える前に、私たち大人がこれからの社会を見据えて変わっていかなければならないのです。
大人が変わる方がより早く影響力があり、「自分自身がなにを大切にして、その生き方を生きること」を問い掛ける生き方が大切になってくるのです。
前回の最後のところで、ある大人が子供に、
「そんなことをしていたら、立派な大人になれませんよ」
その言葉に子供は、悪びれた態度で掛けて行った。
さて、現代の子供に、
「そんなことをしていたら、立派な大人になれませんよ」
「立派な大人ってどんな大人?」
その言葉に大人は、しどろもどろになりバツが悪そうに去って行った。
この後者の子供の言葉は、
私たち大人の社会の投影であり、
子供が素直な気持ちで質問したくなる社会が今ここにあるのです。
それだけ私たち大人自身が、
今の自分の生き方に明確な指針(ガイドライン)を持てていないのです。
では、これからどうしたらいいのでしょうか。
この岐路の時代を生きるためには、どうすればいいのか、どうすればもっと生きやすくなるのかについて今回はお話するという書き出しでしたが、このことは次回にお話したいと思います。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,954 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,110 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,034 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,691 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,669 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,323 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,265 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,866 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31