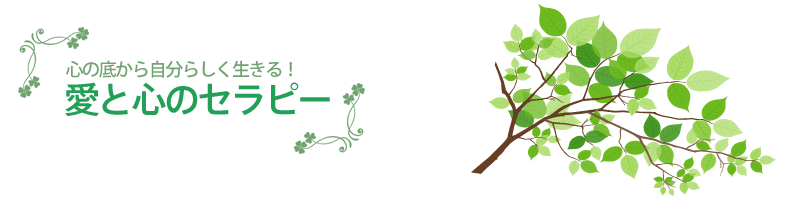「子育て本どおりに上手くいかない(前半)」
PCの不具合で、
久しぶりの投稿となりました。
楽しみにしてくださっていた方、
ほんとうにごめんなさい。
では、2週間ぶりのお話です。
親が自己肯定感を高めた心の習慣を創ること。それが子供の豊かな発想力や前向きな考える力、主体性を育む最大の教育になり、子育ての早道。
すなわち、『感謝を笑顔でする心』を親である私たち大人が育むことにある。
キャリアカウンセラー・心理セラピストの観点から、子供や若者よりも、私たち大人に焦点を当てたお話です。
『Ⅹ.子供若者の未来を創る』
「第13話:子育て本どおりに上手くいかない(前半)」
第2話のところで、「親が子供と接する環境は、日々時間に追われたような生活に感じ、また、経過よりも結果を求める傾向にある」という文の引用を、30年前の本にすでに書いてあったと言うお話をしました。
今回は、私が30年前に読んだ子育て本と今とでは、どうなっているのかについて、お話したいと思います。
私が読む限り、子育ての本質はほとんど変わっていません。今の方が内容の説明はよりわかりやすく、どうすればいいかまで詳しく書いてあると思います。
ただ気になったのは、ハウツウやテクニックなどの方法論の子育て本が、非常に増えたことです。
ピンポイントの課題や技術や資格を習得するならば、そのようなハウツウやテクニック本は、効果的で有効的かもしれません。
しかし、子育てのハウツウやテクニックは参考になっても、いつの時代も子供の情操的なものや感じ方は、頭で理解するものではなく、親御さんや人を通して、子供に浸み込んでいくものなのです。
これを忘れてしまうと、自分は努力しないで、子供だけが良くなってくれたらと期待し、得た知識を言い聞かせたり、押し付けたりしてしまうのです。
そして、問題点だけが目に付くようになり、またそれを解決するための方法が必要となってくるのです。
その影響なのか、子育てに正解はないとよく言われている中で、ある特定の方法論があたかも正解で、自分の子供もそのようになれると、思い込んでしまっている声を聞きます。
ここ近年よく耳にする親の相談で、
「この本にこのように書いてあったのですが…」
「本に書いてあるように子供が成長せず、子育てに自信が…」
「この前聞いた話を、子供にやってみたのですが…」
私はこのような話を相談された時、例えばこのように話します。
続きは次回にお話します。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,955 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,110 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,034 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,691 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,669 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,323 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,265 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,866 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31