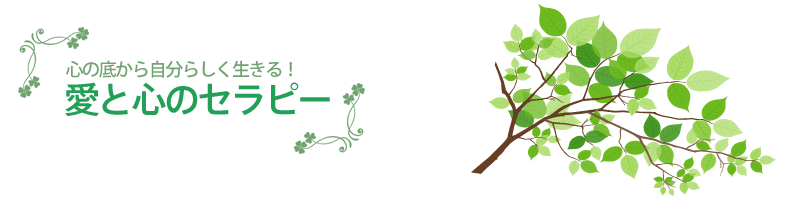『出逢ってくれてありがとう」 第六話
第六話『元カレとの再会』
駅前広場に着いた恭子は、辺りを見回した。元カレの姿はまだなかった。時計は7時5分前を指していた。元カレはいつも遅刻してくるからまだ来ていないのだと思った。
その時、メールに着信があった。健太郎からだった。今着いたという知らせだった。 恭子は、心が痛んだが健太郎には返信しなかった。一瞬用事ができたと返事を打とうかと思ったけれども、健太郎には嘘がつけなかった。諦めて帰ってくれることを望んだ。
恭子は元カレを待ち続けた。元カレにメールや電話をし続けたが、メールの返事もコールは鳴るものの電話にはでなかった。いつも30分は平気で遅れて来るけれど、元カレは必ず来ていた。
時計はいつもの30分が過ぎていた。それから30分待っても元カレは来なかった。メールも電話も同じ結果だった。その間に、健太郎からメールの着信と電話が何度も鳴った。恭子は元カレが恭子にしたように、健太郎にメールの返事も電話にも出なかった。
8時を過ぎた時、恭子はこれ以上待っても元カレは来ないと思った。いつも30分は平気で遅れるけれども、1時間以上待たせたことはなかった。それでも恭子は元カレに来れない何かの事情が起こったのではないか思った。
しかし、メールも電話もまた同じ結果だった。ようやく恭子は諦めて帰ろうとした。健太郎のことが気に掛った。あれから健太郎からのメールも電話もないから、もう諦めて帰ったのだと思った。それは当然のことだと思った。
恭子は、どうしようもない気持ちに打ちひしがれながらも、それでいてまだどこかで元カレに何かが起こって来れないのだと思う自分がいた。
恭子はあてもなく夜の繁華街へと歩いていた。何人ものホストのキャッチが声を掛けて来たが、今の恭子の耳にはその声は届かなかった。
しばらく歩いていると、聞きなれた声に反応して顔をその声の方に向けた。そこには、彼女と思わしき女性の肩に腕を回して楽しそうに歩いている元カレの姿があった。恭子と目が合った元カレは、何事もないように話しかけてきた。
「よう恭子じゃないか。元気にしてたのか。」という側で、彼女らしき女性が元カレに誰かと聞いているのが聞こえた。
「こいつか、昔の彼女だった女だよ。」という元カレの言葉に、
「ずっと駅前広場で待ってたんだよ。」と恭子は振り絞る声で言った。
「待ってた!めでてえ女だな。からかっただけで本気にしたのか?ずっとこいつと一緒だから会う訳ないじゃん。勝手なことぶっこいてんじゃねえよ。」と言って、恭子を嘲笑しながら元カレは彼女と思わしき女の肩に腕を回したまま去って行ったのだった。
恭子は自分のバカさ加減が本当に嫌になった。腹が立たなくなるほど自分が嫌になった。もう生きることがバカらしくなった。涙も出ない自分がおかしかった。完全に精気を抜かれたように、恭子はあてもなく歩き続けた。
気がつくと恭子は電車に乗っていた。外はいつの間にか降り出した雷雨で濡れていた。時折稲光が見えた。それを見た恭子は、その稲光に当たって死ねたらと思ったのだった。
つづく。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,954 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,110 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,034 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,691 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,669 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,323 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,265 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,866 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31