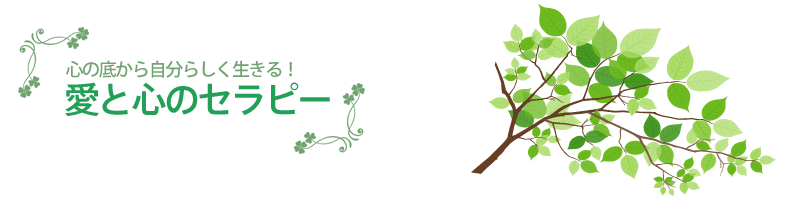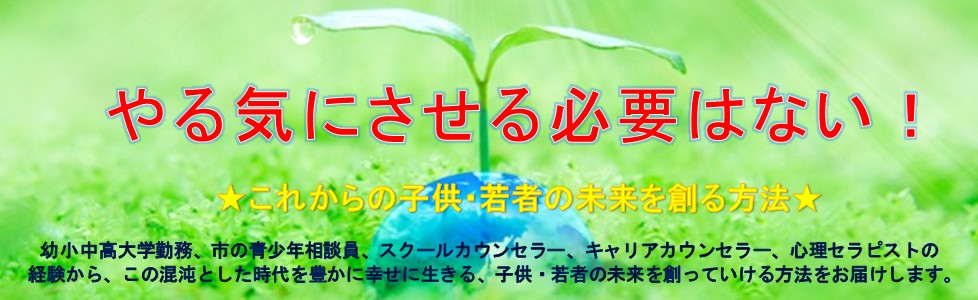「受身的な発想は、愛情ではなく執着を生む」
就職しないできない若者の『未就職予備軍のレジリエンス(回復力)をどう引き出すか?』、キャリアカウンセラー・心理セラピストの観点から、子供や若者よりも、私たち大人に焦点を当てたお話です。
『Ⅸ.就職しないできない若者』
「第49話:受身的な発想は、愛情ではなく執着を生む」
【親が自己肯定感を高めた心の習慣を創ること。
それが子供の豊かな発想力や前向きな考える力、
主体性を育む最大の教育になり、子育ての早道。
つまるところ、『感謝を笑顔でする心』である。】
前回、毎朝見送ってくれる愛犬を見るとき、気分を良くしてくれる(自己肯定感を高めてくれる)と思っている受身的な発想が、『毎日見送ってくれて元気もらうわ。今日も1日頑張れるわ』と思うと、能動的(主体的)な発想になる。
つまり、『愛犬が、私を幸せにしてくれている』という発想から、『私は、愛犬のおかげで幸せになれている』という発想になり、この思考の発想が、私たちの幸せな心を育むというお話をしました。
今回は、その受身的な発想について、触れておきたいと思います。
『愛犬が、私を幸せにしてくれている』と思っていると、心理学的にみると心の奥底ではどんなことを思っているのでしょう。
それは『愛犬がいなくなると、幸せでなくなる』と思っているのです。
心は、この『愛犬がいなくなる』という恐れの感情を解消しようと、必要以上に愛犬に執着し、できるだけ側に置いて世話を焼くことで、癒着の関係ができてしまうのです。
癒着の関係は、自分の主たる意識を相手に明け渡し、相手の意識に同化させることです。
つまり、相手を自分事のように思い、他人の人生を生きようとするのです。
このことは、子育てにも言え、子離れできない原因にもなります。
子供は、家庭中心から学校など社会と接点を持ちだすと、社会での学びが増えていきます。親は少しずつ子供を手放していき、社会に任せていく時期でもあります。
このときに、いつまでも子供のことを不安で心配ばかりしていると、子供の人生に執着し、癒着してしまいます。
癒着とは、親が子供にべったりしがみついているイメージをするとわかりやすいと思いますが、そうなると子供は自由に身動きできず、主体的に生きる力を削がれてしまいます。
すると、親はいくつになっても世話を焼き続ける子供をつくり、子供は自立できずにいつも親に依存し、お互いが依存し合う癒着の関係をつくるのです。
そして、子供が社会人となる時期になると、急に経済的に社会的に自立を求められ、社会適応力の経験が乏しいと、子供が自立できなくなるのです。
私たちの思考は、『主語』を相手や他のものに預けがちになる度合だけ、私たちを依存的にさせるのです。
そして、受身的で依存的な発想からの行動は、無条件や無償の愛情ではなく、相手から嫌われ失うかもしれない怖れに一喜一憂しながら、もっとと思い執着を生むのです。
愛犬や子供は、私たちを幸せにしようと思って行動しているわけでありません。
私たちは、気がつくと『愛犬が、子供が、私を幸せにしてくれている』と思ってしまいがちになって、いつの間にか、『主語』を相手に明け渡してしまうのです。
このパターンは、様々なところに出てきます。
「恋人、夫、妻が、私を幸せにしてくれる」
「会社が、私を幸せにしてくれる」
「お金が、私を幸せにしてくれる」
そう思っていると、人は相手から「そうしてもらえない、そう扱ってもらえない」ときに、不平不満を覚え、腹を立てるわけです。
前回も言いましたが、『愛犬、子供の“おかげ”で、私は幸せになれている』のです。
この『おかげ』という発想は、『感謝』の心です。
私たちは、日々の多忙な生活に追われ、ストレスも感じる度合だけ、人・ものごとの『おかげ』という心に余裕のある『感謝』の視点に立ちにくくなっています。
気がつけば、日々の中で人・ものごとが『当たり前』の発想に過剰に慣れ親しんでしまって、『有り難味』を忘れ出しているのかもしれません。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,954 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,033 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,690 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,668 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,322 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31