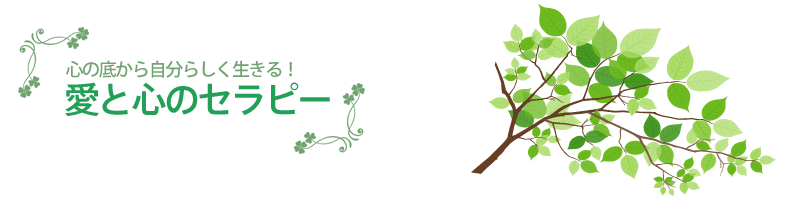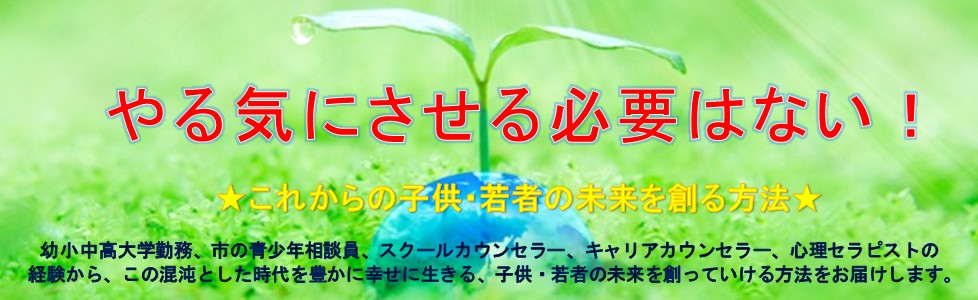「有り難味が希薄化した子供たちの危機②」
親が自己肯定感を高めた心の習慣を創ること。それが子供の豊かな発想力や前向きな考える力、主体性を育む最大の教育になり、子育ての早道。
つまり、『感謝を笑顔でする心』を親である私たち大人が育むことである。
『Ⅸ.就職しないできない若者』
「第65話:有り難味が希薄化した子供たちの危機②」
就職しないできない若者の『未就職予備軍のレジリエンス(回復力)をどう引き出すか?』、キャリアカウンセラー・心理セラピストの観点から、子供や若者よりも、私たち大人に焦点を当てたお話です。
前回、学生の自己PRで、「学生時代に打ち込み困難にぶつかったときに、それをどう乗り越えたか」などの体験談を、書いたり話したりするには、根本的なところで、なにかしらの『感謝』という『有り難味』を体験的に持っているというお話をしました。
今回は、そのことと『有り難味』が、どのように関係しているのかについて、お話したいと思います。
「学生時代に打ち込み困難にぶつかったときに、それをどう乗り越えたか」の体験談を持っている学生は、なにかしら人との関わりの中で、頑張り、支えられ、助けられた体験を、自分の糧としていることを、強く感じます。
そのような学生は、語る言葉に『感謝』や『有り難味』、『謙虚さ』、『人への思いやり』といったものが伝わってくることが多く、なにか自信さえ感じます。
そのことは、学生時代の体験談からもうかがい知れますが、よく聞いていくと、そのルーツは、大学に入る以前の子供時代からそのベースを持っていることに気づきます。
このような学生は、どんどん自分から主体的に行動する傾向にあります。
一方、文章は書けても上手く伝わらなかったり、またなかなか思うように書けず、話せない学生には、大きく次のことが言えます。
前者は、なにかしら人との関わりの中で、頑張り、支えられ、助けられた体験をしたものの、自分が体験した話というよりも、事実関係を述べたり、面接に受かるための方法論に偏ったりする傾向にあります。
いいことを言っているのですが、なにか伝わってこないというケースです。
このような学生には、「面接に受かるための人事受けがすることばかり考えた話になっていないか。自分が体験から本当に伝えたいことはなんなのか。入社してからの思いはなんなのか」などに気づいてもらうことで、奥行きのある生きた言葉になります。
後者はというと、“人に言うほどたいしたことはしていない”と思っている場合が多くあります。自分の体験を糧にできていない、自己受容が苦手なケースが多く見受けられます。
体験したことの大小を気にしたり、他人と比べるのではなく、そこから自分がどんなことを学び、気づいたかを理解してもらい、自己受容を繰り返しながら、自分の体験として落とし込んでいきます。
このような学生は、少し時間と体験のプロセスが必要となることが多く、その結果自信を持てるようになっていきます。
このようなプロセスを信頼して継続していく学生は、目が輝き、生き生きとしてた表情を見せてくれます。
そこで語る言葉には、『感謝』や『有り難味』、『謙虚さ』、『人への思いやり』といったものが伝わってきて、その人が本来持っている魅力までも感じることが多くあります。
このように、自分の体験からなにかしらの『有り難さ』という『感謝』の体験を、心の中に潜在的に持っているのではなく、頭に顕在化させて意識して持つことができると、学生に限らず人というのは、自然と『人のためになにかしたい。役に立ちたい。』という欲求に駆られて、主体的に行動したくなるものなのです。
ただ、頭に顕在化させて意識して持てずに、心の中に潜在的に持っているのだけだと、『人のためになにかしたい。役に立ちたい。』という欲求で終わってしまうのです。
しかし、例に出した学生は、なかなか思うように就職活動ができないだけであって、それよりも、危機を感じるのは、ここからです。
次回は、実際に危機感を覚える「有り難味が希薄化した子供・若者たちの危機」について、お話したいと思います。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,950 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,033 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,690 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,668 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,322 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,828 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31