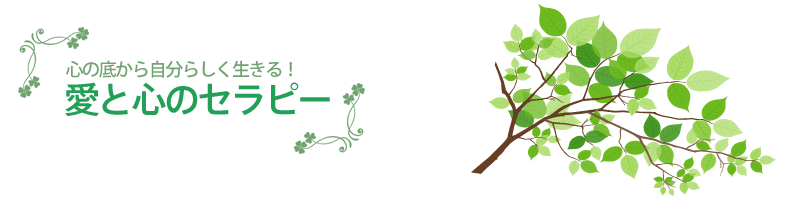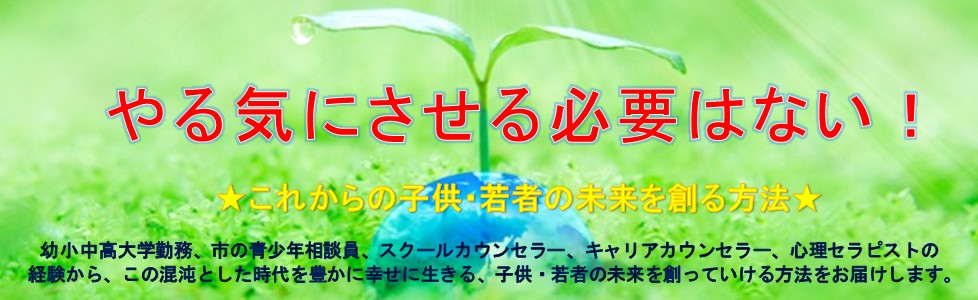「有り難味が希薄化した子供たちの危機③」
親が自己肯定感を高めた心の習慣を創ること。それが子供の豊かな発想力や前向きな考える力、主体性を育む最大の教育になり、子育ての早道。
つまるところ、『感謝を笑顔でする心』を親である私たち大人が育むことである。
『Ⅸ.就職しないできない若者』
「第65話:有り難味が希薄化した子供たちの危機③」
就職しないできない若者の『未就職予備軍のレジリエンス(回復力)をどう引き出すか?』、キャリアカウンセラー・心理セラピストの観点から、子供や若者よりも、私たち大人に焦点を当てたお話です。
前回、「学生時代に打ち込み困難にぶつかったときに、それをどう乗り越えたか」の体験談を持っている学生は、人との関わりの中で、頑張り、支えられ、助けられた体験があり、なにかしらの『有り難味』という『感謝』の概念が培われているように思う、というお話をしました。
今回は、実際に危機感を覚える「有り難味が希薄化した子供・若者たちの危機」について、お話したいと思います。
前回までと同様学生に、「学生時代に打ち込み困難にぶつかったときに、それをどう乗り越えたか」の体験を聞くと、話が出てこないことがあります。
さらに、質問を変えて「学生時代やそれまでの学校生活の中で、なに印象に残っていることは」と聞いても出てこないことがあります。
この傾向のパターンとして、一つには話すのが苦手な学生に見られます。
ただ、文章にするとしっかりとした内容を書ける学生は、そこになにかしらの価値観を持っていて、そこから話を引き出し広げ、人に伝えることを練習していくと、自己表現できるようになります。
となると、話すことも書くことも苦手な人となるのですが、それだけで働くことができないわけではありません。
危機感を感じるのは、その中でも人間形成における人との関係性の煩わしさを避けて生きている人です。
ここで言う人は特に、普通に学校に行き、学校の成績も可もなく不可もなく、話し掛ければ最低限の会話はあり、誰に迷惑を掛けることなく手が掛るわけでもない、ごく普通に見えます。
それだけに、親はなかなか気づけないのですが、客観的にみると家庭にいながら子供が食事付きの下宿人のようになっていることがあるのです。
それでもなにかに熱中するものがあればいいのですが、学校に通うこと以外に社会との関わりが少ない傾向にあり、家でなにするわけでもなくテレビなどを見たりして一日が過ぎていく。
そして、部屋に入ればインターネットの普及により、ネットサーフィン、SNS、動画、最近ではラインなど、実体験の少ない自分にとって都合のいい価値観を持っていくように感じます。
そうして、いざ社会で働かなければならないと思う就職活動の時期になると、はじめてと言っていいかもしれない社会の壁にぶつかり、挫折感を味わうようです。
その代表的なものが、書類応募での不採用、面接での不採用。その他にも、大学での事前準備のための就職ガイダンスや他の学生も参加する合同企業説明会で、働く社会や他の学生と自分との乖離を感じて、気持ちが萎えてしまうのです。
しかも、このような学生は、誰かに相談する傾向が少ないというよりも、相談すると現実の自分を突きつけられることが怖いと思ってか相談することを嫌い、自我流でやることが多く、問題点も振り返ることなく、ただ流れで就職活動をしているように感じます。
でもこのような学生は、根は真面目ですから、大勢の就職活動の時期が過ぎた卒業間際に、人物重視の比較的小規模の企業に決まることがよくあります。
ただ、入社したものの実社会の厳しさに耐えられるだけの考え方や体験、経験が少なく、1年も経たないうちに辞めてしまう傾向にもつながっているように思えます。当然ながら、企業側にも雇用条件などの問題がある場合もありますが。
そして、学生が一度仕事を辞めると、体験したことが働く基準となり、再度就職するには時間が掛り、アルバイトはしても正規雇用の道を閉ざしてしまう傾向にあるのです。
このように体験談が出てこない学生の傾向として感じるのが、社会との接点を持たずに人との煩わしい状況を上手くかいくぐって“日々流されて生きている”ということです。
様々な要因がありますが、深いところで価値観を養う『有り難味』の概念が乏しいことを感じるのです。
日頃、人と関わることが少なく、『ありがとう』と感謝の言葉を述べる機会も、不自由を感じることなく生活できていることが『当たり前化』の中で、
『有り難味』を体験する機会もなく、人としての大切な価値観をつくる機会が減っていることに危機感を覚えます。
その結果、豊かさの影で、約15年前から学生と関わってきて、今の学生の考える力や想像する力、判断する力、そして主体性がさらに失われ、自分に都合のいい価値観に偏っている若者が増えているように感じているのです。
さらに、不自由を感じることなく生活できていることが『当たり前化』することで、危機感を覚えるお話を、次回にしたいと思います。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,948 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,108 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,032 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,689 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,667 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,321 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,263 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,129 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,864 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,827 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31