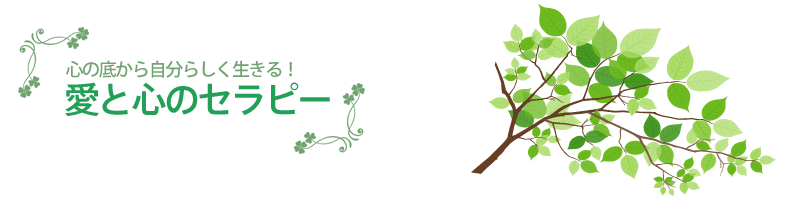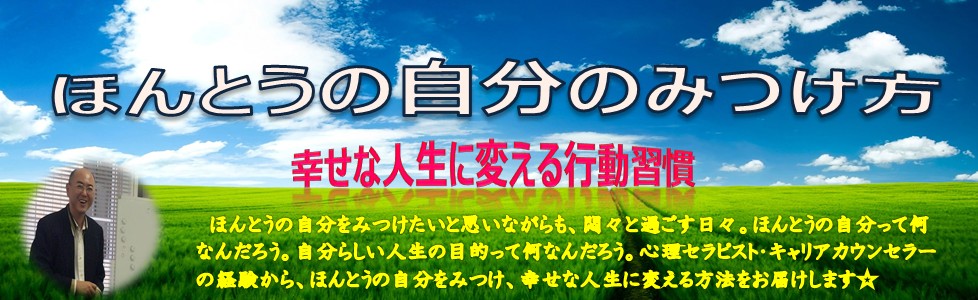「③“お陰様”の心が生まれない若者たち」
『§自分が自分であることが幸せ』
「第38話:③“お陰様”の心が生まれない若者たち」
前回“お陰様”という言葉。
“お陰様で”という言葉にしなくても、
それ以上に“お陰様”という意識そのものが、
体験として身に付いていない危機感を感じると言うお話をしました。
今回は、そのことについて、
もう少し深く掘り下げてお話をしたいと思います。
一昔前になるでしょうか。
東北地方のある記者が、最近の小学生はスーパーで
売っている刺身がどんな魚の形をしているかわからない。
それを揶揄して、最近の小学生は刺身の切り身が
海に泳いでいると思っている、という記事を載せて、
少し話題になりました。
また、塾帰りの親子がスーパーで買い物をしているとき、
テレビのインタビューでその小学生の子供に、
「お米はどうやってできるかわかる?」と聞くと、
「スーパーで作ってる」と答えていました。
この解答には、とても衝撃を受けました。
ものが豊かになり、技術が進歩したとは言え、
そんなことをわからなくなっているんだと、
危惧したことを覚えています。
ここまで知らないのは、一部かもしれませんが、
どうも一部の就職活動をする学生にも、
それに似たようなことを感じるときがあります。
それを感じるときと言うのが、
人との関わりが少ない以上に、
嫌なことや面倒なことを上手くすり抜けて来たと言うか、
楽しいこと、楽しくさせてくれること以外のものごとに、
触れる機会がなかったのかと思うことです。
話をしていても、奥行きがないというか、
言葉を拾って深く突っ込んでも、その体験が
出てこないのです。
それでも出てこないだけだと思い、
今までに旅行に行った話などないのと聞きました。
「旅行に行ったことはあります」
さらに、細かく聞いてみると、
「ただ家族についていって、観光地に行って、
ご飯食べて帰って来た」と。
「風景とか、なにか印象に残るようなことは?
今度私がそこに行くときに、アドバイスある?」
「う~ん、よくわからないです」
「えっ、旅行に行ってなにしてたの?」
「ほぼゲームしてました」と。
私はあえて、お米の作り方について聞いてみました。
「お米はどうやってできるかわかる?」
「田んぼにきまってるじゃないですか」
「そんなことわかってるよ。稲穂がなって、
刈り取って、乾かして、脱穀して、玄米を精米して…」
「えっ、あの粒剥いたら米じゃないんですか」と。
農家の人が手間ひま掛って、害虫からも稲を守りながら
作っている話をすると、とても興味深そうに聞いていました。
そして、中国から来た留学生が、
中国の作物への有害な農薬事情を改善するために、
日本の大学院で勉強し日本の農薬の会社に就職した話を
すると、目を輝かせて聞いていたのでした。
ただ、知る機会がなかっただけ?!
と思ったりした瞬間でした。
“お陰様”という意識は、
“ありがたみ”のことです。
してもらって“ありがとう”の言葉は言えても、
心から“ありがとう”と思える体験が少なければ、
“ありがたみ”も“お陰様”という意識も湧いてこない気がします。
また、そこには人の痛みを理解し、共感できる意識も
乏しくなると言え、それでいて自分の痛みという嫌な感情はわかるから、
その感情を味わいたくないために、
人との関わりや煩わしいことを避けてしまうという、
悪循環に陥ってしまうのかもしれません。
人生の目的や生まれてきた意味はという話に、
“体験”することだと言う話があります。
この“体験”こそが、
“ありがたみ”や“お陰様”の意識が生まれ、
人がひととしての大切なことを気づき成長していくことを
改めて思いつつも、
日本の八百万の神の精神は、なくしてはならない
大切な生きる価値観と強く思うのでした。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,953 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,033 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,690 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,668 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,322 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31