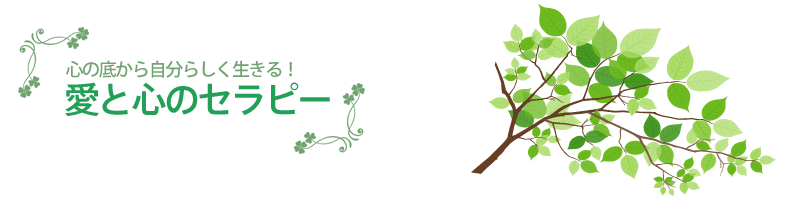「生きている意味なんて」-父との会話ー
第5話「父との会話」
彼女は大阪に帰って来てからも、時間があれば父の元へと通った。姉とできるだけ一緒に、無理な時は一人で実家に帰った。
彼女は見舞うたびに、父がやせ細って行くのがわかった。そんな姿を見て辛い気持ちになる気持ちを押し込めながら、笑顔で接するように心掛けた。
父は入退院を繰り返していたが、時間が経つにつれて入院することが多くなり、この時には病院暮らしが続いていた。と言うより、もう家には帰ることのできない病状になっていたのだった。
父は、尚美が来ると嬉しそうに笑顔を見せた。時折痛みで顔を歪めることもあったが、できるだけ笑顔を作ろうとしている父の姿を見て、父親らしく強く見せようと無理をしていることが、彼女には痛いほどわかった。
そんな父の姿を見て、彼女は居たたまれない気持ちになるのだが、父の笑顔がその気持ちを何とか引き止めてくれた。
ある時、いつも母と一緒に父の病室にいたのだが、母が用事を済ませるために少し出かけて来ると言って、初めて父と二人きりになった。
いつも母が一緒にいたので、彼女はいざ父と二人きりになると何を話していいか戸惑ってしまい、しばらく沈黙が続いた。
そんな情況を父が気遣ってか、口を開いた。
「仕事の方は大丈夫なのか。よく来てくれるけど無理はするなや。」
「大丈夫やよ。店長には話して了解もらってるから。」
「接客の仕事は思った以上に大変やろう。客を選べないしお酒入った相手やからな。ようがんばってると思うよ。」
彼女は父の言葉を聞いて、自分がどこで働いているのか知らないことになっているのに、知っているかのように聞こえた。
彼女はいつも父と会うときは、できるだけ地味な化粧と服装を心掛けて、父に気づかれないようにしていた。
父は、尚美をじっと見つめると、静かなトーンで話し出した。
「尚美、お父さんはもう長くないとわかってる。」
「そんなことないよ、なんでそんなこと言ううん。」
「まあ、そう言わずに聞いてほしい。お父さんは癌や。転移もしてると思う。治療法や自分の症状を見てたら、自分がどんな病気かもわかる。お母さんやお姉ちゃんには言うなや。知ったらどうなるかわかるからな。2人だけの秘密やからな。」と、
父はにっこりと笑いながら言ったが、彼女は父の言葉の重みにしばらく返す言葉が見つからなかった。
彼女は、母も姉も“父は自分が癌のことは知らない”と思っているはずなのに、なぜ自分にだけ話をしたのか気持ちが混乱したのだった。
彼女は父の言うとおり、母にも姉には言わない方がいいと思い、自分の中でしまって置いたのだった。
そして、父の運命の日は近づいていったのだった。
つづく。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,952 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,033 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,690 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,668 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,322 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31