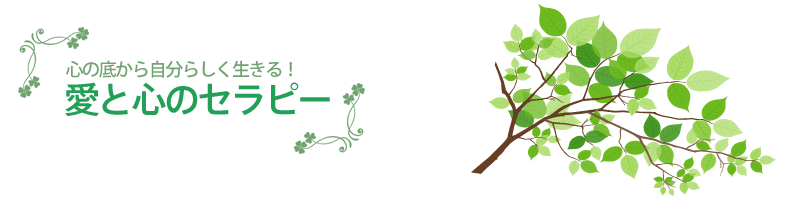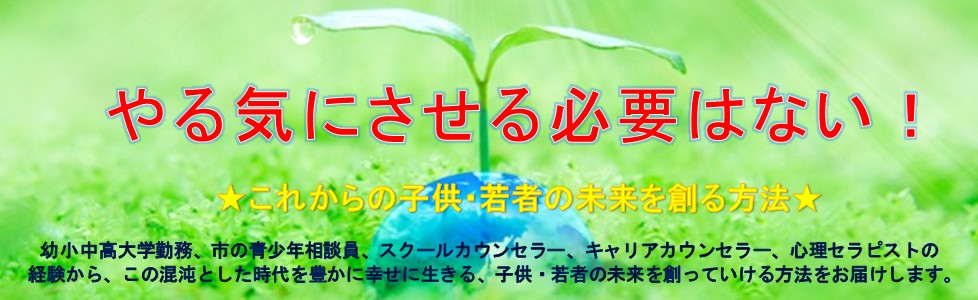「子供のどこを、なにを褒めますか」
◇Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代◇
“こどものこころアドバイザー(心理セラピスト)”の
前中 光曉(まえなか こうぎょう)です。
さて、前回の親御さんからの、
「『子供にやる気を持たせる』ということは、
子供を褒めてあげるということでしょうが、いつも子供を褒めようとすると、
子供に合せすぎて、媚を売るようになると思うのですが」
という質問に対して、三つの観点からのお話です。
まず、一つ目は、「子供のどこを、なにを褒めますか」
自我が確立する小学生までは、いつも子供の価値(いいところ)
を見てあげ、子供の結果はどうであろうと、自分がした、
自分の手で体を動かして、やり遂げたことを褒めてあげることが、
子育てにとても大切なのです。
子供だけでなく人は、その経過を褒められたときに、
自分の価値を褒められたと感じ、満足感と喜びを感じ、
自信になっていくのです。
親御さんには、この『意識と思い』を大前提に持って、
子供と向き合ってほしいと思うのです。
それが、日々の中で『やる気を持たせる』、
自己肯定感を育むことになっていくのです。
これが、子育てで最も大事なことは、
『自己肯定感を高めること』と、言われる由縁です。
ただ、多く子供への期待は、子供がなにごとも上手くこなせ、
早く勉強に取りかかり、早くできあがる、そういう子供を勉強の
良くできる賢い子供と思いがちになります。
そこに親御さんの『意識と思い』が、
結果の善し悪しに目が行きがちになると、子供も結果に意識が向き、
点取り虫という言葉も生まれてくるのです。
また、できなかったときに、自分が理解され受け入れられていない
ような、否定された感じになり、
そうなると、子供だけでなく人は、『やる気』を失っていくのです。
稲には、早稲(わせ)、中稲(なかて)、晩稲(おくて)があって、
それぞれの成長が違うように、人もいろんなタイプがあって人なのです。
兄弟姉妹が多い人はわかると思いますが、
必ず子供はこのように分かれるのです。
それが家族の学びであり、集団の中で生きる社会での、
人間関係の学びになっているのです。
子供の、人のどこに価値を置くか。
それは、相手の行為そのものでなく、相手の存在そのものの価値を
見る習慣を、日々の中で身に付けていくことが大切なのです。
「親の目が、結果の善し悪しに行きがちになっていませんか。」
というのが、この一つ目のお話です。
次回は、二つ目として、
「子供のご機嫌を取るために媚を売っていませんか」を、
お話したいと思います。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,952 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,033 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,690 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,668 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,322 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31