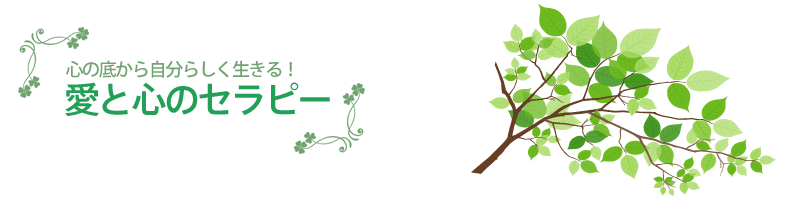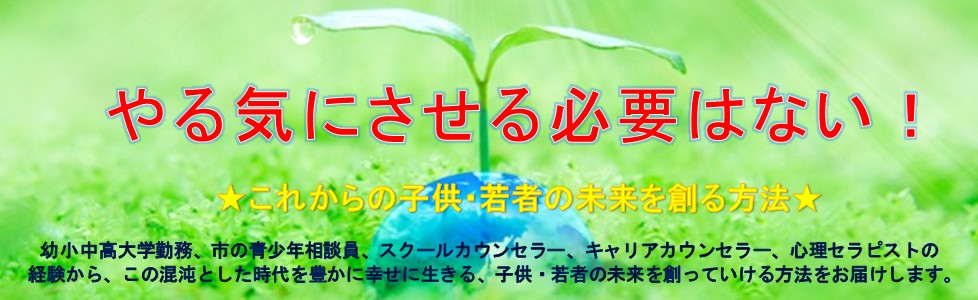「自ら自己肯定感をつくりにくい三つの理由①」
就職しないできない若者の『未就職予備軍のレジリエンス(回復力)をどう引き出すか?』、キャリアカウンセラー・心理セラピストの観点から、子供や若者よりも、私たち大人に焦点を当てたお話です。
『Ⅸ.就職しないできない若者』
「第14話:自ら自己肯定感をつくりにくい三つの理由①」
前回、自己肯定感を高めた生き方が必要不可欠だというお話をしました。しかし、残念ながら私たちの多くは、この心に余裕を持った自己肯定感の高い状態をつくりにくいのです。
今回は、その理由についてお話したいと思います。
その理由とは、根本にあるのは前回にもお話しました、“自己否定を持ちやすい歴史的文化的な時代を生きてきているから”です。
私たちは古来から近年まで、社会は生きるために、物質的に豊かになるために、衣食住という生理的欲求を満たすことを主眼に置いた、生きることそのものに脅かされながら生きてきたのです。
そこで、先人たちや私たちは、その問題を解決するために、教育に力を入れ、国民に物質が行きわたるように大量生産できるようになり、衣食住の心配がほとんどいらなくなるまでなってきました。
しかし、そうなるためには、画一的というみんなが同じ方向を向く教育を必要としました。また、大量生産し、それを売るためには、『創造性や想像力をそれほど必要としないパターン化されたもの』に対応する多くの人材が必要でした。
人はパターン化された方法などに慣れてくると、人はやる気を維持するのが難しくなってきます。
そのやる気を維持させるためには、『何かが欲しいからやる(報酬)』という動機づけや、仕事を放りだしてしまうようなことがあれば業務に支障がでるので、罰となる規則や叱責で『やらなければいけないからやる(強制)』という動機づけも必要でした。
その結果、人々の意識は、その仕事の結果として得られる『報酬(金銭・名誉・地位・賞賛)』にばかり向かっていくのです。
この外部要因によってある行動や態度が動機づけられることを、『外発的動機づけ』と呼びます。
この動機付けの特徴として、『一時的で、他律的で、依存的なやる気』を引き起こします。これが人のやる気の動機づけに偏ってしまうと、『自ら十分に考えて判断し、主体性を持って』行動しなくなってしまうのです。
だから、欲しかったものを手に入れるとすぐに飽きてしまい、みんながするからそうし、世間や周りに流されてしまうのです。
前回『親が伝える子供への生き方』とは、『まず親が心に余裕を持った自己肯定感の高い状態をつくること』と言いました。
それが難しい理由は、多く私たちの行動・態度が、この『外発的動機づけ』の思考体系になっているから、いつも一時的になり、『自ら自己肯定感の高い状態をつくりにくい』のです。
では、どうすればいいのでしょうか。
それは、『外発的動機づけ』と対極にある『内発的動機づけ』が、これからの時代の鍵を握っているのです。
次回は、その『内発的動機づけ』についてお話したいと思います。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,953 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,033 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,690 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,668 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,322 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31