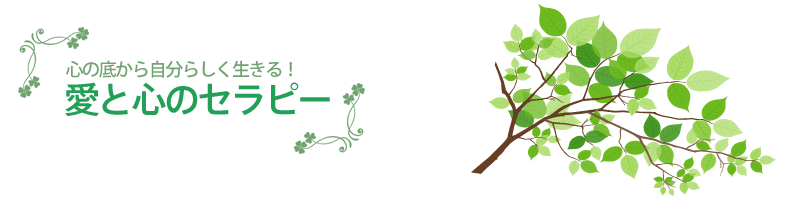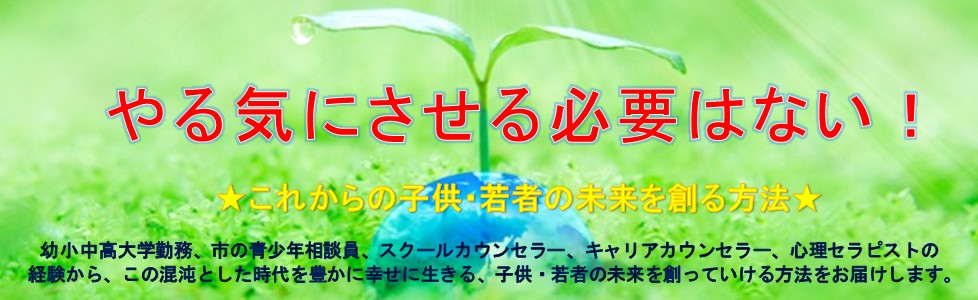「思考パターンを変えて、爪を噛む癖を治す(前半)」
親が自己肯定感を高めた心の習慣を創ること。それが子供の豊かな発想力や前向きな考える力、主体性を育む最大の教育になり、子育ての早道。
つまるところ、『感謝を笑顔でする心』を親である私たち大人が育むことである。
『Ⅸ.就職しないできない若者』
「第62話:思考パターンを変えて、爪を噛む癖を治す(前半)」
就職しないできない若者の『未就職予備軍のレジリエンス(回復力)をどう引き出すか?』、キャリアカウンセラー・心理セラピストの観点から、子供や若者よりも、私たち大人に焦点を当てたお話です。
前回、自分軸である『自分らしくある』心の状態に、『どう自分が生きるか、どう考えて行動するか』が、大切になってくること。
私たちの時代は、新しい時代へと転換期にいること。
日頃私たちの不安や心配事の目の前にある状況を変えるためには、ネガティブな思考パターンである役に立たなくなった『観念』を変えていく必要があること。
心が平安で軽やかな状態なときに、『自分が望む幸せな現実を引き寄せ、現実を創ることができる』こと。
それが『豊かな実りある人生を生きること』につながると。
今回は、「第56話:思考パターンを変える、爪を噛む子供の例え」の続きとして、爪を噛む癖が治ったケースと、ネガティブな思考パターンである役に立たなくなった『観念』を変えていく思考パターンを変える方法のお話をしたいと思います。
まずは、爪を噛む癖が治ったケースからお話します。
子供が爪を噛む行為は、不安から落ち着かない状態になってイライラしていることが多く、情緒不安定になっていることが見て取れます。
家以外との社会属性がまだ少ない子供のイライラは、どこから来るのでしょうか。
その答えは、家庭であり、親御さんとの関係に多くルーツがあります。
心理セラピーのカウンセリングの現場でも、このように親御さんに原因があるお話をすると、一瞬面食らったような反応をされます。
それもそのはず、親御さんは子供が爪を噛む相談に来ているのですから、問題は子供にあると思うからです。
親御さんは親御さんで子育てに不安になりながらも、愛する子供のためにできるだけの事と思い、いつも自分のことは後回しにしながら一生懸命子育てをしているわけですから、そう思うのも無理はありません。
爪を噛む子供の育ての状況を冷静にかつ客観的に見ていくと、生活や子育ての不安から、つい子供への思いが勢い余って、無意識で親の一方的なペースで子供にあれこれしゃべり過ぎたり、結果をすぐに求め過ぎたり、自分の意のままにならずに感情的になったり、質問攻めにしていることがあります。
この頃の子供は親が大好きで嫌いになれませんから、すべてを受け止めようとします。
そして、子供なりに親の期待に日々応えようとするのですが、子供ができることは大人と比べると小さいわけです。
子供にとって、そのできないことがプレッシャーとなったり、心の許容量を超えてバランスを崩して、自分が自分で無いような(自分軸からずれた)不安からイライラしてしまうのです。
さらに子供は大人のように、起こっている状況を思考で理解することができません。
子供は子供になりにその気持ちのやり場を解放しようとします。それを外に向けると物を使って攻撃的になったり、時に人を噛んだりすることもあります。
すると当然、注意されたり、大声で叱責されたり、時に叩かれたりして、子供は恐怖から気持ちのやり場を閉じ込められてしまいます。
そうなると、今度は内に意識を向けだし、体調を崩しがちになったり、不安からのイライラを解消するために、固い爪に歯で力を加えて噛み切ることで発散しようとするのです。
ここで大事なのは、親御さんが、子供に爪を噛むことを止めさせることではありません。
子供自らが、爪を噛むことを止めることです。
“止めさせる”ことは、コントロールです。心理的な負荷は、矯正ではなく強制なのです。
このことは、このブログの大テーマ『やる気にさせる必要はない』に通じていて、『子供をやる気にさせる』のではなく、『子供にやる気を持たせる』ことと、同じ原理です。
そのためには、親御さんが、“子供を”ではなく、“子供自らが”止めようとする環境をつくることが大切になってくるのです。
つまり、親御さんが“主”で、子供が“従”の発想から、いかに両方が“主”の関係をつくることが大切になってくるのです。
そのことは、子供の“主体性を創る”ことと関係し、誰もが人生の主人公の発想につながってくるのです。
この“主”の関係をつくることが、子供が爪を噛むことを止めさせる方法にもなり、その方法は後半でお話したいと思います。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,954 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,033 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,690 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,668 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,322 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31