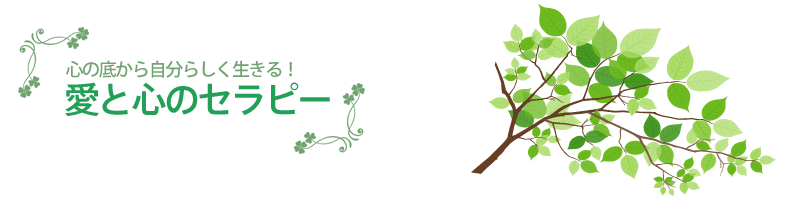「子育ては子離れ(後半)」
親が自己肯定感を高めた心の習慣を創ること。それが子供の豊かな発想力や前向きな考える力、主体性を育む最大の教育になり、子育ての早道。
すなわち、『感謝を笑顔でする心』を親である私たち大人が育むことにある。
キャリアカウンセラー・心理セラピストの観点から、子供や若者よりも、私たち大人に焦点を当てたお話です。
『Ⅹ.子供若者の未来を創る』
「第8話:子育ては子離れ(後半)」
前回の前半で、心に寄り添う子育てが必要となり、それが子離れにもなってくる。でも、ここで、言葉の観念の罠に多く陥るお話の続きです。
子離れと言う言葉を意識すると、多く子供を自立させないといけないとか、子供を強引に引き離されるような気持になったり、逆に心を鬼にして忍として子供を突き放し、距離を置くような気持になります。
それが罠に陥る、言葉の観念の誤解の元なのです。
そうではなく、子供の価値や希望(期待ではなく)を見続け、待つ(心に余裕を持ち信頼を寄せる)姿勢を持って、平常心で子供と接するだけのことなのです。
甘えてくれば、甘えさせてあげればいいのです。
子供が甘えてきたりするのは、寂しさや不安があるからです。
子供はその不安が安心に変わると、また外の世界につながろうとして、社会を知っていくのです。
しかし、親の傾向として、平常心を忘れ、あまりにも、子供、子供と考えすぎて、他から得た知識や方法論をすぐに子供に注入しがちです。
前にも言いましたが、それは得た知識や方法論を、子供に言い聞かせようとしているだけなのです。
かわいさあまりに成長する子供に必要以上に頭で理解させようとすると、親の権威で子供をコントロールすることにもなり、子供が社会で自律するための自立を形成して行く機会を、失わせてしまうことにもなるのです。
親が話を聞いた後、親自身が自分のものの考え方を育てたり、人間を高めながら自分に落とし込み、親という身を通して、子供にしみこむものなのです。
それが子育てで大切な、ふれあいであり、子供と一緒に学ぶ情操教育になるのです。
子育てに答えがないと言われるように、完璧な子育てはありません。
だから、子供の心に寄り添いながら、一緒に成長する姿勢が大切になってくるのです。
そのためにも、親がいつも平常心を保てる心に余裕を持つ時間をつくり、心掛けていくことが、親自身の心の習慣をつくっていくことになるのです。
次回は、子供を叱る厳しさの中にある真の優しさについて、お話したいと思います。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,954 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,033 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,690 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,668 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,322 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31