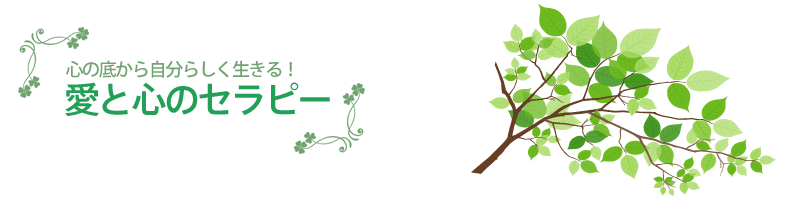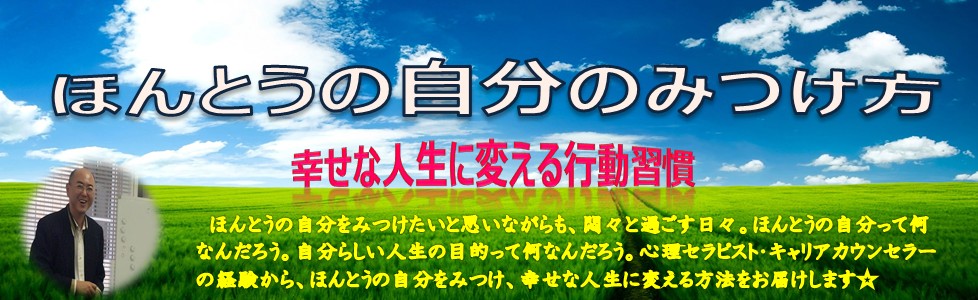「人生を飯ごう炊飯にたとえると」
『§自分が自分であることが幸せ』
「第24話:人生を飯ごう炊飯にたとえると」
桜が満開に咲き誇り、花見やバーベキュー。
キャンプには少し早いですが、
人生を飯ごう炊飯にたとえて、なぜ人生の生きる力である
「新社会人基礎力」の考えを持つことが大切なのか、
再度違った視点からお話したいと思います。
ここは無人島。一人の若者が漂流しました。
ここにはガスはありません。電気などもありません。
若者は漂流した船の中を見ていると、
そこには運よく飯ごうとお米がありました。
お腹も減り、生きるためにご飯を炊くことにしました。
しかし、いざご飯を炊こうと思ったのですが、
飯ごうでご飯なんて炊いたことがありません。
知らないわけですから、ご飯が食べられません。
そこで、「もっと生きる力を学んでおけばよかった」と、
思えばいいのですが、できないものは仕方がないと諦めて
その場に寝転がりました。
そして、若者はお腹いっぱいになっている姿を想像して
空想の世界に耽っていました。
そこに、先に漂流した一部始終を見ていた男がいました。
その男は、飯ごうもお米があるのになんてことだ!と思い
若者に近づいて行きました。
「その飯ごうとお米、いらないのか?」
「どうせ使い方もわからないから、いらない」
「そこでなにしてる?」
「誰かが助けに来るのを待ってる」
「助け?もう俺はここに5年もいるぞ!」
気がつくと、少しは危機感を覚えたのか、若者は男と
なにやら親しげに、飯ごうでご飯を炊いていました。
「飯ごうに入れる水かげんが大事。水かげんを間違えると
芯のある固いご飯だったり、べちゃべちゃだったりする。
火も直接大きな木に火をつけてもつかないから、
こうやってはじめに小枝や枯れ葉などに火をつける。
それから、徐々に太い木に火を移していく。
そして、この火かげんがとても難しい。
弱火、中火、強火といっても、ボタン一つの炊飯器とは
わけが違う・・・。青年ご飯炊いたことあるのか?」
「さあ、なければコンビニで買ってくれば済むことだし」
「ここをどこだと思ってるんだ。無人島だぞ!まあいい。
火かげんだ。“はじめちょろちょろなかぱっぱ”だ」
「なにそれ、ご飯を炊くおまじない?」
「火かげんのたとえだ。つぎ!火かげんは難しいから
炊き上がる時間もわからない場合は、炊き出して飯ごう
から吹きこぼれがあり、そのときの音が消えいい匂いが
してきたら飯ごうを裏返して蒸らす。青年わかったか?」
「ぜったいムリ!」
「最近の若者は・・・」と思いたところですが、
実際にこの約20年学生という若者と接していて、
本来高校までに培って来たであろう人生の生きる
力が身に付いていない学生が増えことを実感します。
しかし、そんな学生を見ていて、思うことがあります。
それは、若者たちが自ら望んでそうなったわけではなく、
大人がつくってきた社会で生きて来ただけなのです。
ゆとり世代と言われたりしますが、
若者が自ら望んでそのような教育を受けたのではないのです。
今まで書いてきた「新社会人基礎力」は、
若者だけでなく大人へのキャリア(生き方)と自己形成を
再度呼び起こすメッセージでもあります。
このたとえはご飯の炊き方を忘れ、らくで簡単なことが
あたかも当たり前になることで、モラルが低下してきた、
私たち大人への警鐘でもあるのです。
心理学者のマズローこの2016年の約50年以上前に、
『人間は生まれながらに創造性や革新(方法・習慣などを
改めて新しくすること=イノベーション)をもたらす力を
備えている』。
そして有効的な問いかけは、
『ひとはなぜ創造し革新しないのか』と。
私たちが生きるこの時代は、
この問いに答える生き方が求められ、
それが『ほんとうの自分をみつける』ことの、
第一歩のような気がします。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,952 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,033 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,690 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,668 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,322 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31