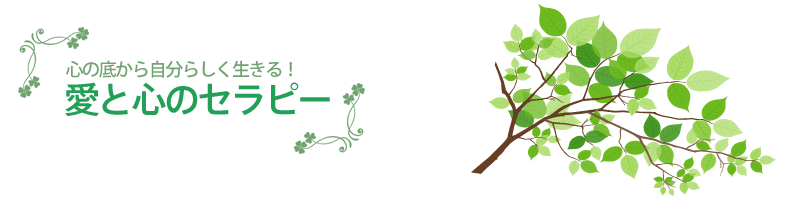「誰かに本気で寄り添ってほしいと思うこと」
『§まっすぐに生きるのが一番』
「第40話:誰かに本気で寄り添ってほしいと思うこと」
哲也が意図しないまま「殺し文句」を言った瞬間から、哲也と優花はお互いを認め合った唯一の存在として、恋人同士の関係になった二人の物語。
前回、哲也は愛犬の小鉄と散歩をしながら、小鉄の寄り添う温もりや学生時代の女の子のさりげない『不思議な寄り添おうとする力』に、改めて人の温もりを噛みしめていたのだった。
哲也は小鉄との散歩を終えると、優花やおばあちゃん、妹がいる母屋に戻って来た。小鉄に水を飲ませると、自分ものどが渇いていることに気づきどうしようかと思っていると、おばあちゃんがグラスに麦茶を持って来てくれていた。
哲也はまたしても、今回ここに誘ってくれたことや、意味ありげなひと言と言い、まるで自分の心がわかっているかのような振る舞いに、度肝を抜かれる思いだった。
「さあさあ哲也さん、小鉄とのお散歩ご苦労様でした。ここの麦茶は井戸水で作っているから、どうぞ召し上がってください」
哲也はその麦茶を一気に飲みほすと、優花が声をかけて来た。
「おかえり」
「てっちゃんおかえり~」
「慣れ慣れしいわね、ほとんど話もしていないのに」
「いいじゃん。じゃなんて呼べばいいの?“哲也”はおかしいでしょう」
「あたりまえでしょう!」
「じゃお兄さんは?私お兄さんほしかったんだ」
「お兄さんはおかしいでしょう!」
「お姉ちゃん結婚するんでしょう。だったら私のお兄さんになるわけだから、お兄さんでいいじゃん。キャラ的にお兄さんって言うようより“お兄ちゃん”かな」
「なに勝手なこと言ってるのよ。ねえ哲也、妹に何とか言って」
「えっ」
哲也は“結婚”と言う言葉にドギマギしていて、どう返事をしたらいいのかわかなかった。
「なんでもいいよ」
「じゃ”お兄ちゃん“ね」
「“お兄ちゃん”はおかしでしょう。まだそうなったわけじゃないんだから」
「じゃ今結婚するって決めたら。そしたら“お兄ちゃん”でいいじゃん」
哲也は妹の“結婚”と言う言葉に緊張が走り、背筋が伸びる思いがした。
「そんなことこれからどうなるかわからないでしょ」
哲也は優花のその言葉を聞き、今度は不安な気持ちに駆られた。
「そこでボーっと立ってないで、ここでお姉ちゃんにプロポーズしたら」
「なに言ってるの、失礼でしょ。そんなこと言ったら哲也が困ってるでしょ」
「そんなこと言って、一番困ってるのお姉ちゃんじゃないの?お姉ちゃん困ったこととかあったら、すぐドナルドみたいに口の先尖らせるし」
「ほらほらその辺りで話しをやめて、せっかくのお料理が冷めてしまいますよ。まだ今日あったばかりだし、哲也さんでいいんじゃないかな」
「やだ」
「“お兄ちゃん”はちょっと変な感じがするから、てっちゃんでいいよ」
「じゃ“てっちゃん”ね。お墨付きをいただきました~」
「もーほんとになんて子なの。哲也ごめんね。世間知らずで」
「てっちゃん、私けっこう料理がんばったんだよ。そこに座って。私がご飯よそってあげるから。じゃーんたけのこご飯。熱いからフーフーして食べてね。お姉ちゃん、おばあちゃんたちのご飯よそってあげて」
哲也は優花が妹を見る目が怒っていると思った。哲也はこんな戦況がはじまりそうな状況になったことがなく、どう振る舞えばいいのかわからなかった。
哲也はふと頭を過った。このまま妹の勢いを受けたら、きっと後で優花に『なに妹にデレデレしてたのよ!』と怒られる気がした。
哲也はこの状況は悪い気はしないが、後がややこしくなりそうと思った。
ただ自分はどう振る舞えばいいのか、自分ができることは、なされるがままこの状況を受入れるしか思い浮かばなかった。
「あらあら、なにかお姉ちゃんより妹さんの方が彼女みたいね。いいわね~若い人が来ると私も気持ちが若返る気がするわね」と、
ここの母屋のおばさんがこの状況に火に油を注ぐように会話に入って来た。
哲也は妹の出方が気になりドキドキした。
「でしょう。私のほうがお姉ちゃんよりお似合いでしょう」
哲也は優花の顔を見た。そしてふと思った。
『このような情況は、最後は自分が悪者になって終わる』と。哲也は自分に火の粉が降って来るのを覚悟した。
「ハイハイ。そうね、あなたのほうがお似合いね」
哲也は優花の冷静な返答にドキドキした。
「なによ、つまんないの」
哲也は思った。『えっ!“つまんないの?”どう言うこと?』
すると妹は興味がなくなったのか哲也から離れ、小鉄のほうへ歩いて行ったのだった。
哲也は妹が小鉄の頭を撫でているのを見ていた。小鉄は目を細めて嬉しそうな顔をしていた。
哲也はその妹の姿を見ていると、なんだかさみしい気持ちになった。
そして思ったのだった。『この子、寂しいんだ』。
そう思うと何だか自分を見ているようだった。
そして、哲也は思った。
『この子も、心の底から誰かに本気で寄り添ってほしいんだな』と。
つづく。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,952 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,033 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,690 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,668 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,322 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31