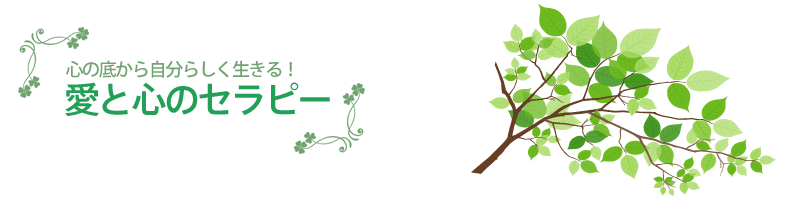「“別に”の言葉が気になる」
『§まっすぐに生きるのが一番』
「第41話:“別に”の言葉が気になる」
哲也が意図しないまま「殺し文句」を言った瞬間から、哲也と優花はお互いを認め合った唯一の存在として、恋人同士の関係になった二人の物語。
前回、哲也はすねる妹が愛犬の小鉄の頭を撫でる姿を見ていると、自分もなんだか寂しい気持ちになってきた。
そして、『この子も、心の底から誰かに本気で寄り添ってほしいんだな』と、哲也は思ったのだった。
哲也は、そこにいる妹が自分を見ているかのように思っていた。
哲也は妹の側に行って、声を掛けてあげたいと思った。
それは小鉄や学生時代に失恋した時に、小学生の女の子が不思議にそっと自分の心に寄り添ってくれたように、自分もそうしたい気持ちに駆られた。
哲也は優花の方を見た。優花は楽しげに食卓の団らんの中にいた。おばあちゃんもその輪の中にいた。
哲也は妹の側に行っていいかどうか迷った。
優花は妹が哲也にちょっかいを出すような押し問答に乗らずに、冷静な対応をした。その結果、妹は話の骨を折られたかのような形になって、『つまんないの』と言ってすねて小鉄のところへ行った。
哲也はそんなことを思うと、このままそっとしておくべきかと思った。
しかし、自分の心は今すぐにでも妹に側に行って声を掛けてあげたい気持ちになった。
哲也はそう思ったものの頭をよぎるものがあった。
この状況は、よくあるお母さんが子供を叱ったときに、子供は悲しそうな顔をしてすねる。それを見ていたお父さんが子供に近づいて慰める。
そこまではいいのだが、それをまるでお母さんが悪者であるかのような慰め方をする。
お母さんは意味があって子供に叱ったにも関わらず、ときに子供を甘やかさないために突き放したにも関わらず、お父さんがのこのこと子供のところに行って甘い顔をする。
そして、お母さんは腹が立つ!
『2人そろって私を悪者?!子供に甘い声を出して、私に恨みでもあるわけ!子供に好かれようと、なに善人ぶってるのよ!子育てする私の身にもなってよ!』と、
ブチ切れる!!
哲也も、もしここで妹のところに行くと、自分もそんな風に振る舞ってしまうだろう。そして、妹は自分に寄り添って来るように甘えてくれるだろう。
でも、あとが面倒臭くなりそうだと頭をよぎる。
優花から声を荒げるように怒られたことはないが、『なんで妹のところに行ったの?』と、冷静で低いトーンで聞いて来る優花の声を思い出すと、ヘビに睨まれる蛙のように身震いする自分がそこにいた。
でも、心は妹の側に行ってあげたい。
哲也は再び、優花の方を見た。楽しげに話をしている。
おばあちゃんも当然ながらその会話の輪に入っている。
哲也は妹が小鉄を撫でている背中を見ていると、自然と腰を上げた。
「哲也さん、もうご飯のおかわりはいいのかしら?じゃお茶でも煎れましょう。優花ちゃん哲也さんにお茶でも煎れてあげてもらってもいいかしら」
哲也はおばあちゃんに声を掛けられ、優花に座るように促され、哲也はなにか後ろ髪を引かれる思いのまま妹の方を一瞥すると、再び椅子に腰掛けたのだった。
哲也は半分うわの空で会話の輪に入っていた。
哲也は沈黙の時間、今の情況を振り返る。
『絶妙のタイミングでおばあちゃんが声を掛けて来たのは、自分は妹のところに行くべきでなかったということだろうか。それとも偶然?必然?そんなわけは・・・』
「さてと、お腹も満たされましたわね。哲也さん、日頃味わうことのできないこんないいところに来たのに、優花ちゃんとなかなか話す時間がなかったわね。後片付けは私たちでしておくので、二人で散歩でもしてきたらどうかしら」
「そうよ、二人で散歩でもしてきたら。あとはおばばたちがやっておくから、デートしてきてちょうだい」
「哲也久しぶりだし、お言葉に甘えて少し散歩に行こっか」
哲也には断る理由もなく、妹がいる方向をちらっと見ると、優花と一緒に席を立った。
哲也は正直優花と散歩する気分ではなかった。
二人で歩きながらも妹のことが気になっていた。
そんな楽しげに見えない哲也に、
「どうかしたの?体調でもわるいの?」
「いや、別に」
「ならいいけど、“別に”って言うときって、なにかあるときに言うよね」
哲也はぎくりとした。そしてこう思うのだった。
『めんどくせー!!』
それ以上聞いてくれるなオーラを放つ哲也であった。
つづく。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,952 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,033 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,690 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,668 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,322 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31