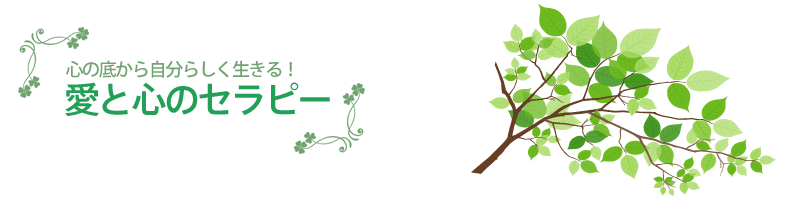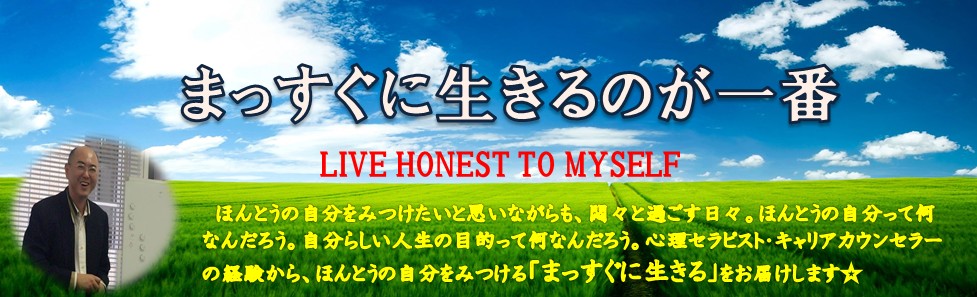「自ら活動的に学ぶ大切さ」
『§まっすぐに生きるのが一番』
「第74話:自ら活動的に学ぶ大切さ」
哲也が意図しないまま「殺し文句」を言った瞬間から、哲也と優花はお互いを認め合った唯一の存在として、恋人同士の関係になった二人の物語。
前回は、先の見えない将来の不安などは、どうしても先を見てしまうと気が失せってしまうもの。
だけど目の前のすべきことに懸命に取り組んでいると、集中力も高まり、未来に対する明確な答えが見えてくるから、今やるべきことをやることが大切だと。
今回は自ら活動的に学ぶ大切さを、哲也と優花は運転を代わるために立ち寄ったコンビニで、何気ない会話の中で話していた。
「やっぱり私はこっちの方が性に合っているかな」
優花は哲也と運転を代わり、助手席に座りながらスマホをいじっていた。
「俺も運転は嫌いじゃないから、ハンドル握ってる方がいいかな」
「じゃこれからは運転哲也に任せようかな。見て、面白い絵があるわよ」
優花はスマホで見ていた絵を、哲也に見せた。
「なにこれ、なんの絵?」
「中世ナポリのフェデリーコ二世大学の授業風景だって。この絵を見ると、何百年前も今の日本の大学の授業風景も変わらないんだって」
「なるほどね。講義型の授業風景は、今も大学では主だよな」
「それもそうなんだけど、そうじゃなくて“授業態度”だって」
「授業態度?」
「三つぐらいあるみたいだけど、哲也わかる?」
「うん、三つね」
「あっこれよね。へー笑えるね。ほんと昔も今も変わらないわね」
「あっこれか。なるほど笑えるな」
「右上の方の女性は、おしゃべりしてるわね。その下の男性は、横を向いて完全に寝る体制になってるよね。その前の男性は、ボーっとしたまま前を向いて教科書かノートみたいなものも持ってないわね」
「ハハハ、大学時代講義の授業ではよくみかけたな。優花は前列の真ん中に座ってる女性だよな」
「そんな優等生じゃないわよ。それに一番前になんか座る勇気なかったし。哲也は前のボーっとしてる男性だったりして。よく考えることが好きみたいだし」
「まああれに近いけど、後ろの方の席でね」
「講義型の授業って知識を習うにはいいけど、興味がないものには集中力が続かないわよね。どうしても受身的になるし。
そう言えば、最近はアクティブラーニングといって、高校生、大学生、社会人、企業研修など、参加者中心型の学習手法が多くなってるみたいね」
「能動的な学習って呼ばれてるやつだよね」
「一般的にはバディワークやグループワークのような形ね。元々はゼミや演習などでやるケースメソッドらしいけど、自ら主体性を持って考え力を養うためのものだったみたい。
だけど、大学で自ら主体性を持って考える力が低下してきたことで、高校まで広がって、今では小学校でもこのアクティブラーニングが取り入れられているんじゃないかしら」
「ゲームやインターネットが登場して、本を読まなくなって活字離れもするようになって、考える力や想像する力が落ちてるって言われてるからな。
それに講義型の授業は“聴覚”が基本だけど、今は写真や映像など“視覚”で情報を得ることが多くなったから、聴覚中心の授業では考えたり想像したりする力がないと、学習効果も上がりにくくなっているのかもしれないな。
て言うか、なにかのデータで、スマホやラインなどに依存する傾向が強い中高校生の成績は、そうでない中高校生と比べると低くなってた。
つまりそれって、視覚中心になって聴覚する力が劣ってくるから、講義型の授業ではよっぽど先生の話し方が興味を引かないと、集中できなくなってくるんじゃない?」
「そうね、それも一理あるかもね。聞いたことを自ら考えたり想像したりすることって、自分に意識が向かうけど、目で見えることって外に自分の意識が向いて情報を取るから、そんなによく考えたり想像したりしなくていいかもね。
そうなると自ら考えたり想像して、それを確かめるために積極的に活動的に学ばなくてもいいから、それって興味あることにしか関心を移さなくなってくるんじゃない?
つまり、ものごとを好きか嫌いか、楽しい楽しくない、興味があるない、面白い面白くない、もっと言うと心に響くか響かないと言った感覚でものごとを判断したり、行動するようになるんじゃない?
自ら活動的に学ぶことって主体的に体験することだから、嫌なこともあるし、失敗することもあるわけよね。
そうやって人は成長していくものだと思うんだけど、哲也のところの人事担当者が言っていた、人と関わりがないこと以上に、自分勝手にものごとを判断する若者が増えてるってことよね」
「そういう若者とそうでない若者が二極化してるってことか」
モノを所有する時代から、心を豊かにする時代になってきたからこそ、自ら活動的に学ぶことが大切になってくる。
それは、自分と向き合いながら、自らが主体的に、自分を律した生き方が求められてくると言える。
なぜなら、心を豊かにする時代とは、愛と感謝と思いやりつながりに満ちた世の中を創り出すことであり、自ら創り出さずに外に求めてばかりいる限り、創り出せないのだから。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,950 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,033 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,690 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,668 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,322 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,828 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31