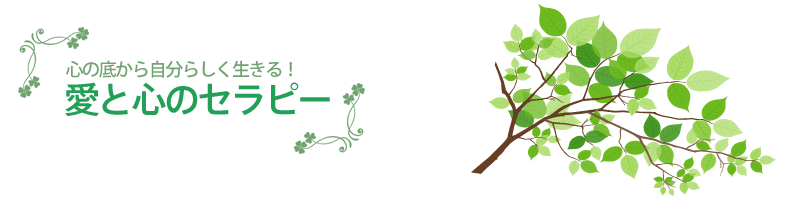メソッド実践編:「再度ありがとうの実習の大切さ③」
◆心の底から自分らしく生きるメソッド◆
「光曉和尚の愛と心のセラピー物語」
~私、自分らしく人生を生きます~
※はじめてこられた方は、
この物語の『登場人物』・『あらすじ』を 先にお読みいただければ幸いです。
§ 再度ありがとうの実習の大切さ③
前回、和尚は、『幸せ』以外にも『ありがとう』から派生した言葉があり、また自分の意識の広がりや『気づき』について写真を使って、実際に体験してもらった。そして、その意識して見ることが、なぜ忘れていってしまうのかについて、これから話をしようとしたのだった。
「有里さん、瑞枝さん、誠くん。写真のひよこちゃん探しで、だいぶ『ありがとう』の実習がイメージできたと思います。そして、自分の意識を広げる感覚も理解できたのではないでしょうか。では、なぜ、私たちは、この意識して見ることを忘れていってしまうのでしょう。
内的な心理的要因と外的な環境要因の二つの観点からお話したいと思います。
まず内的な心理的要因なのですが、
私たちが見るものごとを、これはこういうもんだと思い込んだり、
子どものように感情を出すのは大人として分別に欠けるとか、
いい大人がとか、食い気が張ってるとか、変な子と思われるとか、欲が深いとか、
いろんな制限を自分の思考や心に掛けてしまっていることが考えられます。
そうすると、どんどんものごとを単一的に狭い視点で捉え、感情を感じることも制限されるようになり、つまり、意識の視界が360度あったものが、目に見える視界が狭まった意識でものごとを捉えてしまうようになるのです。
例えて言うなら、円柱形のガラスコップを上下左右あらゆる角度から立体的に見ていたものが、真正面から見ると長方形に、真上から見ると丸に見えるように面で捉え、意識の広がりも同じことが言えるのです。
前回の話を例に取ると、少し極端ですが、ネコを見て『ネコ』、
花を見て『花』、そこに咲いてることすら気づいていないかもしれないですね。
『目を引く服』とか、譲り合っているのを見てただやり過ごして『・・・』とか、
『電車が来た』とか、『青い空』とか、『スマホを見て笑ってる』とか、
『高校生は期末テストか』とか、『ほしいカバンを持っているんだ』などと、
あまり感性を働かさずに視覚だけでものごとを捉えるようになるのです。
さらに考えられる外的な環境要因として、
私たちの生活している社会が、物質的に豊かになったのはいいのですが、今度はものが余りだして品不足に困ることはなくなって、そのおかげで生きることへの不安が減って心が安定したのですが、
ものがいつもあるのが当たり前になっていき、気がつくとそこに『ありがたみ』の意識が薄れてきた時代にもなってきたのです。
また、様々なことが便利になり、その便利さに慣れ過ぎてしまうと、それが当たり前になり、その物質的な恩恵の裏側で、ものごとをあまり考えずに、らくで簡単に人の欲求を満たしてくれる便利な時代にもなってきたのです。
それがまた、私たちの疲れた心を軽減してくれたり、渇望した心を満たしてくれるものだけに、知らず知らずのうちにその習慣になれていくと、らくで簡単に手に入る自分の欲の損得でものごとを決めるようにもなってきたのです。
他にも経済が成熟したことや生活スタイルの変化などの理由もあるかもしれませんが、大きくこの二つが意識して見ることを忘れさせてしまう理由だと考えられます。
そうなっていくと、ものごとを表面で捉え、ものごとを深く考えたり想像することもあまりしなくなり、短絡的にものごとを選択するようになっていき、その結果、ものごとに流されやすくなり、情報に流されやすい生き方にもなってくるわけです。
そのことは今までお話してきたように、『ありがとう』という『本来有ることは難しいものごとが、有り得ることへの感謝=有り難い』、すなわち『ありがとう』の中にある『有り難み』も希薄化してきているのです」
和尚はここで、次の話にいく前に一旦言葉を止めたのだった。
つづく
次回明日10月28日(月)は、引き続き、
メソッド実践編:「再度ありがとうの実習の大切さ④」をお話します。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。 心より感謝いたします☆
※この物語は、実話にもとづいたフィクションであり、登場する人物など、実在のものとはいっさい関係がありません。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,952 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,033 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,690 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,668 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,322 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31