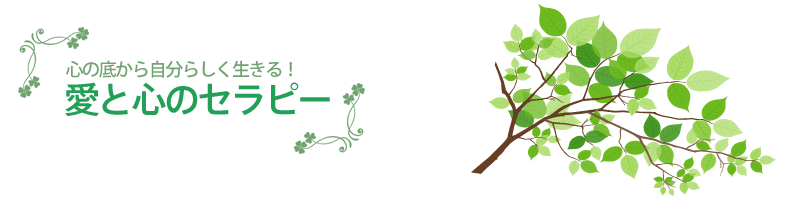メソッド実践編:「こんな私でいいんだ モニター有里編」
◆心の底から自分らしく生きるメソッド◆
「光曉和尚の愛と心のセラピー物語」
~私、自分らしく人生を生きます~
※はじめてこられた方は、
この物語の『登場人物』・『あらすじ』を 先にお読みいただければ幸いです。
§ こんな私でいいんだ モニター有里編
前回、和尚は瑞枝に「こんな私でいいんだ」という言葉を使って、メソッドの実習をしていった。和尚はより深い心の領域に入るために、心理セラピーも使って瑞枝の感情を解放していった。
そして、和尚は、瑞枝だけでなくモニターになってくれている有里と誠にもメソッドの実習をしていったのだった。
和尚は、瑞枝のメドッドの実習をひとまず終えて、ローテーションで順番に対象者を変えていき、瑞枝に信念となる「こんな私でいいんだ」の言葉を、有里、誠とメソッドの実習を繰り返しすることで落とし込んでいった。
「さて、有里さんの番ですね。やり方はわかりましたよね。それでは実習をはじめていきましょう」といって、和尚は有里にメソッドの実習をはじめていった。
和尚は、有里と実習をはじめていくと、自分の感情を素直に表現していった。
有里は、明るくて積極的で、しかも活動的で社交性のある女性特有の柔らかさと知性と落ち着きを感じさせる女性だった。
しかし、有里はその表の部分とは裏腹に、ものすごく自分をちっぽけに扱っている自分がいた。
和尚はその部分を有里に気づかせながら、メソッドの実習を続けていった。
和尚は有里とメソッドの実習をしていると、有里の性格の意外な一面が出てきた。
有里は短大を卒業した頃まで、好きな人にぞっこんになり、世話好き過ぎて恋愛で失敗することが多かった。
社会人になり多忙な生活を送っていくと、そこで受ける男性からのアプローチが、自分への性的な対象として見られている感じを受けることが多々あり、過去の恋愛の傷も合わさって男性への不信感が増していった。
有里は、30歳を超えて年齢的なこともあって、結婚して幸せになりたいと思っていたが、気づかないところでそのことが恋愛、結婚への足かせになっていた。
有里はこのメソッドの実習をするまで、そのことには気づいていなかった。それだけ、自分の中で深く恋愛に対して、そして男性の自分への性的なアプローチが不信感を増大させていた。
人が思い込む気持ちは様々だと思うのだが、有里は「こんな私でいいんだ」と言うほどに、一般的に男性が好む性的な豊かな体の部位の自分を嫌っていた。
流れからいくと、有里の嫌っている体を肯定して、嫌っている自分を受入れて統合していくのだが、和尚はさらに踏み込んで有里に感情に入っていった。
有里は人を好きになると一図になると言っていた。しかし、最近では客観的に男性を見る自分がいるとも言った。
それは、裏を返せばのめり込む恋愛は怖いと言っているのと同じだった。
有里の話を聞いていると、有里の母親はしつけなどに厳しい人だった。そのことは、知らず知らずのうちに、有里を従順すぎるぐらい手の掛らないいい女の子にしていった。それは、有里にとって母親が言うことは絶対になっていた。
母への考えは、社会人になって一人暮らしをするようになって様々な価値観を知り、だんだんとそんな思いは薄れていった。
でも、男性には、不信感からそれ以上自分の感情をさらけだすことはなかった。
和尚は、有里にそれらの観念を作ったルーツを探っていくと意外なことがわかった。それは、有里が、母からも父からも、そして祖母からも、女の子ということで愛されて育ってきた。
有里の育った環境は、都会から離れていて、昔ながらの古風な女性とはという習慣が根強くあり、その暗黙のルールの上で育てられてきたようだった。
有里のルーツは、両親や祖母の女性にとってよかれと思った習慣が、逆に有里の持つ活発的な特性を抑圧していたのだった。
有里が「こんな私でいいんだ」と認めることは、深い潜在意識で両親や祖母の期待に応えない裏切ることになるという観念が出てきた。
有里は「こんな私でいいんだ」という度に、「こんな私ではあってはいけない」という感情が湧き上がってきた。
その「こんな私ではあってはいけない」という思いは、有里に取ってとても根深い観念になっていた。
なぜなら、そのことは両親や祖母の期待以上に、有里が育った環境、その地域では当たり前の価値観を否定することになり、無意識なところで自分が社会に生きる存在意義にも大きく関わるような観念の重圧に苛まれていたのだった。
有里の邪魔をする観念は、自分が思い込んで役に立たなくなった観念をゆるす以上に、自分が生きている大きな社会をゆるさなければならなかった。
有里は、古き時代の習慣を身に付けていったことで、簡単に言えば社会人となって一人暮らしをして、新しい社会の都会的な習慣などとの不整合性に混乱し、怒りを溜めていたのだった。
和尚は、有里の怒りを解放させ変容させていきながら、有里が持つビジョンとも言うべき自分がしたいことを受け止める怖さ、引き受ける怖さを無意識に感じていることを見逃さなかったのだった。
つづく
次回明日12月20日(金)は、
メソッド実践編:「こんな私でいいんだ モニター誠編」をお話します。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。 心より感謝いたします☆
※この物語は、実話にもとづいたフィクションであり、登場する人物など、実在のものとはいっさい関係がありません。
カテゴリー
- 幸せにくいのないような人生を生きる
- 優花と哲也の愛を育む物語
- まっすぐに生きるのが一番
- 自分が自分であることが幸せ
- 幸せになるための新社会人基礎力
- はじめに(やる気)
- Ⅰ.子育ての悩みはつきないもの
- Ⅱ.子育ては自己肯定感を高めること
- Ⅲ.自己肯定感を育みにくい理由
- Ⅳ.自己肯定感を高める子育て
- V.やる気にさせる必要はない!
- Ⅵ.これからはやる気を持たせる時代
- Ⅶ.子供にやる気の方法(基礎編)
- Ⅷ.子供にやる気の方法(体験談編)
- Ⅸ.就職しないできない若者
- Ⅹ.子供・若者の未来を創る
- 50代からの自分らしく輝く方法
- ありがとうの効果秘訣
- ありがとう10か条
- セミナー・ワークショップ開催報告
- メソッド物語序編
- メソッド物語本編
- メソッド物語実践編
- 今を生きる4つの心の法則
- 気づきの宝箱
- 奇跡の婚活物語
- 奇跡の婚活物語の手記
- 徒然思うままに
- 観念が創り出す心の罠
- 理想のパートナー観念の罠
- 心で気づく心のメカニズム
- 心のセラピー物語Ⅰ
- 心のセラピー物語Ⅱ
- 心のセラピー物語Ⅲ
- チャンスはどこにでもある
- 出逢ってくれてありがとう
よく読んでいただいている記事
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) - 12,952 views
- 孤独な人に手をさしのべたとき、その人は癒され、あなたは贈り物を受け取る! - 9,109 views
- 「子供・若者の職業観(働く目的)が変化している?」 - 4,033 views
- 『もう一つのエピローグ』(「出逢ってくれてありがとう」) - 3,690 views
- 自己ヒーリングしていた!(私のありがとう体験談③) - 3,668 views
- ありがとうの達人のなり方 - 3,322 views
- ワクワクする創造性は、あなたの心の欲求を満たしてくれる! - 3,264 views
- 「感謝の日記帳」 - 3,131 views
- 四.進歩進展、現状打破のいしづえとは - 2,865 views
- 「『主体性』と『自主性』との違いを言えますか」 - 2,829 views
最近のコメント
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 前中光曉 より
- 奇跡のような転機(私のありがとう体験談④) に 高木淳子 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に 前中光曉 より
- 「自分らしく輝くために知っておきたいこと(前半)」 に ゆみこ より
- 彼女に催促したありがとう に 藤原康典 より
最近の投稿
- 「次世代をつくる若者の反映は私たち大人」
- 「自信が持てない若者の自信が持てない言動」
- 「日本は便利になり若者がダメになる?」
- 「やっぱり“ありがたみの心”を知る人は強い」
- 「中学生の就業体験からの学び」
- 「無力さの中にある才能」
- 「二つの文章。どちらが幸せな生き方?」
- 「人生の主人公は自分自身だと自覚する時代」
- 「“おはよう”の挨拶が起こした奇跡」
- 「足の裏の米粒」
- 「人生頼って、頼られて、」
- 「人生愛して、愛されて、」
- 「危ないひとりよがり…」
- 「なにかのために時間を使うのではなく…」
- 「私はこういう人間だからと決めつけて」
- 「今の自分は、自分のことがそんなに嫌いじゃない」
- 「ポジティブな心を育む三つの心と五つの気」
- 「忘れない三つの心」
- 幸せにくいのない人生を生きる
- 「ありがとうを言う数だけ人は幸せになる?」
アーカイブ
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
2025年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31